奇跡の君
Open Menu
レイデ夫妻とその一行が王都に戻ったのは、ちょうど秋の音楽会が終わった頃だった。
リナレーア=レイデが望んだ冒険の日々は一年ほどで終わってしまったが、彼女はがっかりなんてしなかった。その腹の中には、新たな未知の存在が宿っていたからだ。
夫、ザイラスとの赤ん坊である。
腹の少し膨らんだリナレーアが懐かしいレイデ家の屋敷に戻るとそこには姉のディートリンデが待ち構えていて、懐妊が発覚してもすぐ旅をとりやめなかったことでザイラスを詰り、今後出産までは自分がリナレーアに付き添って無理をさせないようにすると宣言した。
ザイラスが、眉をひそめながらもその宣言に抵抗しなかったのは、彼自身すでにヘンリック王から膨大な量の仕事を言い渡されていたからだ。一年間の休暇のツケである。恐怖という感情を取り戻してなお無鉄砲なところのある妻の監視役として、ディートリンデはこの上ない適役だ。だからこそ彼は、屋敷にディートリンデの部屋を用意したし、エンブリー公爵に苦情を入れたりしなかったのだ。
しかし王都帰還から二ヶ月が過ぎ、山のようであった仕事が少しずつ減ってくると、ザイラスは苛立ちをつのらせるようになってきた。
なにせ、リナレーアと二人きりになれる時間がないのである。
ディートリンデは前に宣言した自分の任務に忠実であった。朝から晩までまるでひっつき虫か何かのように妹にくっついて離れなかったのである。初めての出産を控えていたリナレーアもまた姉を頼りにしているようだったので、ディートリンデに出て行けと強く言えないのもザイラスには耐え難かった。
そしていよいよ産み月に入ろうとする冬の日、ザイラス=レイデは実力行使に出たのだった。
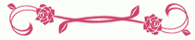
「なんなのこれは。どういうこと?」
ディートリンデ=エンブリーは不愉快そうな様子を隠そうともせずに言った。
「もちろん、君を迎えにきたんだよディー」
その日レイデ家には訪問者があった。
短く刈り込まれた暗めの金髪にごつごつとした肉体を持ったその人は、ヘンリック=ゲーテ=デーメル……つまり、この国の王である。
ヘンリック王は今、芸術家の国として知られる小国ビレビスを魔物と共存できる国に造り替えようとしている。実際少し前から王城では、数人の魔物を正式雇用しているらしい。かつて魔物使いとしてヘンリック王の命令のもと国の内外を飛び回っていたザイラスの今の仕事は、魔物に関する法整備や居住地の確保、市民への情報開示など魔物関連の雑事全般であった。
「迎えにきたですって? 呼んでないわ」
しかし一介の公爵令嬢であるはずのディートリンデは、自国の国王に対して冷たい言葉を投げつけた。
「城に帰って仕事をなさい」
「はっはっは。君の口から紡がれるなら罵倒さえ春を呼ぶ歌声のように聞こえるよ」
「気持ち悪いから近づかないで変態」
ヘンリックは持っていた赤い薔薇の花束をディートリンデに押し付けると、そのまま彼女をぎゅうと抱きしめた。
「ちょっと! やめてよ!」
「やぁリナレーア。身体の調子はどうだい?」
ヘンリック王は、恋する人を抱きしめたままその背後にいたリナレーア=レイデに声をかけた。姉妹は空いている部屋で赤ん坊の服に刺繍をしているところであったが、リナレーアは持っていた刺繍糸を針山に戻し、立ち上がった。
「ええ、おかげさまで順調です。先日は、贈り物をいただいてありがとうございましたヘンリック様」
「男でも女でも楽しみだ。ヴァルターも心待ちにしているだろう」
一年前に起こした騒動の責任を取って、実家であるエンブリー公爵家領で蟄居処分となっている兄ヴァルターからは、定期的に手紙と贈り物が届いている。
リナレーアは今にも破裂しそうに膨らんだ自らの腹を、愛おしく撫でながら微笑んだ。
「生まれる前からこんなに愛されて、この子は幸せですわ」
「すべては君の人徳だよリナ。さて、ディー。着替えはこちらで用意しているからこのままでいいよ。僕とでかけよう。ああマーティン、彼女の外套だけ持ってきてくれるかね?」
「はい、かしこまりました」
控えていた執事が頭を下げてディートリンデの外套を取りに行く。
「きゃあ!」
ディートリンデが悲鳴をあげたのは、ヘンリック王に抱き上げられたからだ。
「離して! 離しなさい! ヘンリック!」
「そんなに暴れないでディー。君を縛り付けて馬車に放り投げてもいいんだよ」
ヘンリック王がにっこり笑ってそう言うと、その本気を感じ取ったディートリンデはきゅっと口をつぐんだ。そのやりとりを見てリナレーアは驚く。
(まぁ珍しい。ヘンリック様がお姉様を黙らせておしまいになるなんて)
ヘンリックがディートリンデにアプローチして手ひどく拒絶されるのはいつものことであるが、ヘンリック自身姉のそんな反応を楽しんでいる様子があった。少なくともリナレーアが見ている前で、ヘンリックがディートリンデの抵抗を許さなかったのはこの時が初めてだったのである。
「今日はね、大事な話があるんだ。だから今日だけ僕に付き合ってほしい。リナレーア、今日一日だけ姉君をお借りしてもいいね?」
そんなことを言われて嫌だとも言えない。
「……はい」
こくりと頷いた時、姉がすがるようにこちらを見ていたがリナレーアは心を鬼にして二人を見送ることにした。
ヘンリック王がクソ王であることは別にして、彼がディートリンデに恋をしているのは本当だ。もう十年以上にも及ぶ彼の恋は、なんらかの形で決着をつけなくてはならないことだった。そしてそのためには、姉は彼から逃げてはいけないのだ。
「あの、ヘンリック様。くれぐれもお姉様に乱暴なことはなさらないでくださいね」
それでも釘をさすようにしてそう言うと、すでに彼女に背を向けて部屋から出て行こうとしていたヘンリックは、顔だけ振り向いて片方の目を瞑ってみせた。
「君の姉君は五体満足でお返しするよ。約束する」
「お気をつけて」
リナレーア=レイデは手を振って二人を見送ると、重くなった腹に手をあてて「ふぅ」と息を吐き先ほどまで座ってた椅子に再び腰掛けた。
最近腹がとみに重く感じるようになってきた。腹の中の赤子はとても活発で、夜であっても関係なくリナレーアの腹を蹴り上げたりする。男の子かもしれないとエイダに話すと、「調べたところ胎内で活発かどうかは生まれてくる赤ん坊の性別に影響しません」と返されてしまった。
本当はこういう話もゆっくり夫としたいのだが、王都に戻ってきてから彼はずっと忙しく働きまわっていてろくに屋敷にも帰ってきていない。最近はたまにリナレーアのいる部屋に顔を出してくれたりするのだが、ディートリンデが間に入ってきてまともに会話もできないうちに仕事に戻ってしまうのだ。
姉がずっと側にいてくれることが心強いのは確かだが、気詰まりに感じるのも本当であった。
(少し前まで、ザイラス達と旅をしながら四六時中一緒にいたのが夢のようだわ)
リナレーアはもう一度息を吐いた。
すると背後からふわりと抱きしめられて、覚えのある温もりが耳元に押し付けられた。
「リィナ」
少し低く甘い声。
リナレーアは一瞬呼吸を止めた。
「あなた」
「ちょっとそのままじっとしてろ」
そう言われたので振り向こうとしたのをやめる。夫は背後からぎゅうぎゅうと妻を抱きしめ、子猫のようにその鼻先をすんと鳴らした。
やがて満足したのか、腕の力を緩めたザイラスがリナレーアの正面に回って膝をつき目線を合わせる。
久しぶりに間近に見た夫は一緒に旅をしていた時よりも少し痩せていたが、顔色は悪くなかった。
「お仕事を抜け出してこられたの?」
リナレーアはすっと手を伸ばすと夫のほおに触れた。すると彼はそちらに顔を傾けて、漆黒の瞳でじっと妻を見つめる。
「今日はもう終わりだ。ずっとお前と一緒にいる」
「え?」
リナレーアは目をぱちくりとさせた。
「邪魔者もいなくなっただろう? 今日は夜まで二人きりだ」
「まぁ……あなた、もしかして」
ヘンリック王がディートリンデをさらっていってしまったのを頭に思い浮かべる。あれはザイラスの差し金だったのだろうか。
「クソ王もいい加減王妃を決めろとせっつかれてるんだ。いい機会だから無理やり王妃にするなりきっぱり振られるなりしてこいと言っておいた」
「まぁ……」
「リィナ、立てるか? こっちにおいで」
立ち上がったザイラスに腕を引かれ、リナレーアは部屋の隅に置かれた長椅子の方へ歩いた。すると先にザイラスが腰掛け、その脚の間に座れとばかりにぽんぽんと座面を叩かれる。
リナレーアは少し躊躇したが、断るのもおかしいのでどきどきしながらちょこんとそこに腰掛けた。すると待ってましたとばかりに背後から腕が回される。ザイラスは身をかがめてリナレーアの肩に自分の顎を置いた。その手は大きくなった妻の腹を撫でている。
「動くか?」
「……はい、とても元気な子ですよ」
久々の甘い雰囲気に、リナレーアはどきどきするのが抑えられない。顔が赤くなっているのが彼に見つからなければいいと心の中で願った。
ザイラスはその手をリナレーアの腹にあてて少し待ったが、やがて不満そうに言った。
「動かないじゃないか」
「今はきっと寝ているんだわ」
リナレーアはくすりと笑った。
お腹の子が動くのを夫にも見せてあげたい。たまにだがはっきりと、これは足なのだろうなとわかる時があるのだ。この中には本当に、自分たちの赤ん坊が宿っている。
しかしザイラスの切り替えは早かった。
「そうか、それは好都合だ」
そう言ったかと思うと、ぐいとリナレーアの顎を掴んで口付ける。突然のそれにもちろん抵抗などしなかったが、やがて口づけが深くなっていくとリナレーアは混乱した。
唇が離れた時、リナレーアは夫と自分の持つ温度が同じになっているのを感じたし、それが恥ずかしくて彼の顔を見られなかった。
「……恥かしいわ」
突然のキスに準備のできていなかった心臓が飛び出しそうだ。こんなのは、胎児にもよくないに違いない。
「ヤドリギ、というのを知っているか?」
しかしザイラスはリナレーアの言葉など聞いていない様子で言った。
「他の樹に寄生して生えてくる灌木だそうだ。西の方の国にはこの時期クリスマスという祭りがあって、その祭りの日に、ヤドリギの下に立っている相手にはキスをしてもいいということになっているらしい」
「くりすます、ですか……」
なんの話かわからない。そっと顔を上げて夫を見ると、彼の眼差しは触れたら火傷をしてしまいそうな熱を帯びていた。
「数週間前その話を聞いた時は、この屋敷の中を毎日クリスマスということにしてお前の部屋の天井にくまなくヤドリギを敷き詰めれば、たとえそこに姉君がいようが関係なくお前にキスできるのかと思った」
「……そんなこと、なさいませんよね?」
「それくらい、お前が足りなかった」
ザイラスが再び強くリナレーアを抱きしめる。
その力の強さと耳元で漏れたため息に、彼も自分と同じくらい寂しかったのだと感じられてリナレーアは切なくなった。夫の腕に自らの手を絡め、顔を夫にすり寄せる。
「わたくしもです。ずっとこうしてゆっくりとお話したかった」
「俺はお前に触りたかった」
そう言いながら夫の手が妻の胸のふくらみに伸びてきた時、リナレーアの腹をぽこんと蹴った者がいた。
「あ! あなた! 今赤ちゃんが蹴ったわ!」
リナレーアはそれまでの色っぽい雰囲気を霧散させる声を上げた。
「ほら! 触ってみてください!」
不埒な行為に及ぼうとしていた夫の手を掴んで自らの腹に当てさせる。すると今度は胎児がぐいーと母の腹を押した。
「ね? わかりました?」
「……」
振り向けば、夫が今まで見たことのないような顔で妻の腹を覗き込んでいる。
「どうです? 元気な子でしょう?」
「……」
するとザイラスはすっかり毒気の抜けた様子で息を吐くと、背もたれに体重を預けて天井を仰いだ。
「あなた?」
どうしたのかと心配になって体勢を変え夫に向き直ったリナレーアは、困ったように笑う彼を見てどきりと胸を高鳴らせた。彼が演技でなくこんなふうに優しく笑うことはあまりないのだ。
「まったく、お前には敵わないなリィナ」
なんのことを言われているかわからない。けれどザイラスは、今度は柔らかく妻を抱きしめると、「俺がいなかった間のことを教えてくれ。久しぶりにゆっくり話そう」と言った。
そしてそれは、リナレーアがずっと望んでいたことなのだった。
——この五日ほど後、レイデ夫人は元気な男児を出産した。
その男児はゲイル=レイデと名付けられ、多くの祝福を受けた。
リナレーア=レイデが望んだ冒険の日々は一年ほどで終わってしまったが、彼女はがっかりなんてしなかった。その腹の中には、新たな未知の存在が宿っていたからだ。
夫、ザイラスとの赤ん坊である。
腹の少し膨らんだリナレーアが懐かしいレイデ家の屋敷に戻るとそこには姉のディートリンデが待ち構えていて、懐妊が発覚してもすぐ旅をとりやめなかったことでザイラスを詰り、今後出産までは自分がリナレーアに付き添って無理をさせないようにすると宣言した。
ザイラスが、眉をひそめながらもその宣言に抵抗しなかったのは、彼自身すでにヘンリック王から膨大な量の仕事を言い渡されていたからだ。一年間の休暇のツケである。恐怖という感情を取り戻してなお無鉄砲なところのある妻の監視役として、ディートリンデはこの上ない適役だ。だからこそ彼は、屋敷にディートリンデの部屋を用意したし、エンブリー公爵に苦情を入れたりしなかったのだ。
しかし王都帰還から二ヶ月が過ぎ、山のようであった仕事が少しずつ減ってくると、ザイラスは苛立ちをつのらせるようになってきた。
なにせ、リナレーアと二人きりになれる時間がないのである。
ディートリンデは前に宣言した自分の任務に忠実であった。朝から晩までまるでひっつき虫か何かのように妹にくっついて離れなかったのである。初めての出産を控えていたリナレーアもまた姉を頼りにしているようだったので、ディートリンデに出て行けと強く言えないのもザイラスには耐え難かった。
そしていよいよ産み月に入ろうとする冬の日、ザイラス=レイデは実力行使に出たのだった。
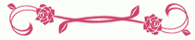
「なんなのこれは。どういうこと?」
ディートリンデ=エンブリーは不愉快そうな様子を隠そうともせずに言った。
「もちろん、君を迎えにきたんだよディー」
その日レイデ家には訪問者があった。
短く刈り込まれた暗めの金髪にごつごつとした肉体を持ったその人は、ヘンリック=ゲーテ=デーメル……つまり、この国の王である。
ヘンリック王は今、芸術家の国として知られる小国ビレビスを魔物と共存できる国に造り替えようとしている。実際少し前から王城では、数人の魔物を正式雇用しているらしい。かつて魔物使いとしてヘンリック王の命令のもと国の内外を飛び回っていたザイラスの今の仕事は、魔物に関する法整備や居住地の確保、市民への情報開示など魔物関連の雑事全般であった。
「迎えにきたですって? 呼んでないわ」
しかし一介の公爵令嬢であるはずのディートリンデは、自国の国王に対して冷たい言葉を投げつけた。
「城に帰って仕事をなさい」
「はっはっは。君の口から紡がれるなら罵倒さえ春を呼ぶ歌声のように聞こえるよ」
「気持ち悪いから近づかないで変態」
ヘンリックは持っていた赤い薔薇の花束をディートリンデに押し付けると、そのまま彼女をぎゅうと抱きしめた。
「ちょっと! やめてよ!」
「やぁリナレーア。身体の調子はどうだい?」
ヘンリック王は、恋する人を抱きしめたままその背後にいたリナレーア=レイデに声をかけた。姉妹は空いている部屋で赤ん坊の服に刺繍をしているところであったが、リナレーアは持っていた刺繍糸を針山に戻し、立ち上がった。
「ええ、おかげさまで順調です。先日は、贈り物をいただいてありがとうございましたヘンリック様」
「男でも女でも楽しみだ。ヴァルターも心待ちにしているだろう」
一年前に起こした騒動の責任を取って、実家であるエンブリー公爵家領で蟄居処分となっている兄ヴァルターからは、定期的に手紙と贈り物が届いている。
リナレーアは今にも破裂しそうに膨らんだ自らの腹を、愛おしく撫でながら微笑んだ。
「生まれる前からこんなに愛されて、この子は幸せですわ」
「すべては君の人徳だよリナ。さて、ディー。着替えはこちらで用意しているからこのままでいいよ。僕とでかけよう。ああマーティン、彼女の外套だけ持ってきてくれるかね?」
「はい、かしこまりました」
控えていた執事が頭を下げてディートリンデの外套を取りに行く。
「きゃあ!」
ディートリンデが悲鳴をあげたのは、ヘンリック王に抱き上げられたからだ。
「離して! 離しなさい! ヘンリック!」
「そんなに暴れないでディー。君を縛り付けて馬車に放り投げてもいいんだよ」
ヘンリック王がにっこり笑ってそう言うと、その本気を感じ取ったディートリンデはきゅっと口をつぐんだ。そのやりとりを見てリナレーアは驚く。
(まぁ珍しい。ヘンリック様がお姉様を黙らせておしまいになるなんて)
ヘンリックがディートリンデにアプローチして手ひどく拒絶されるのはいつものことであるが、ヘンリック自身姉のそんな反応を楽しんでいる様子があった。少なくともリナレーアが見ている前で、ヘンリックがディートリンデの抵抗を許さなかったのはこの時が初めてだったのである。
「今日はね、大事な話があるんだ。だから今日だけ僕に付き合ってほしい。リナレーア、今日一日だけ姉君をお借りしてもいいね?」
そんなことを言われて嫌だとも言えない。
「……はい」
こくりと頷いた時、姉がすがるようにこちらを見ていたがリナレーアは心を鬼にして二人を見送ることにした。
ヘンリック王がクソ王であることは別にして、彼がディートリンデに恋をしているのは本当だ。もう十年以上にも及ぶ彼の恋は、なんらかの形で決着をつけなくてはならないことだった。そしてそのためには、姉は彼から逃げてはいけないのだ。
「あの、ヘンリック様。くれぐれもお姉様に乱暴なことはなさらないでくださいね」
それでも釘をさすようにしてそう言うと、すでに彼女に背を向けて部屋から出て行こうとしていたヘンリックは、顔だけ振り向いて片方の目を瞑ってみせた。
「君の姉君は五体満足でお返しするよ。約束する」
「お気をつけて」
リナレーア=レイデは手を振って二人を見送ると、重くなった腹に手をあてて「ふぅ」と息を吐き先ほどまで座ってた椅子に再び腰掛けた。
最近腹がとみに重く感じるようになってきた。腹の中の赤子はとても活発で、夜であっても関係なくリナレーアの腹を蹴り上げたりする。男の子かもしれないとエイダに話すと、「調べたところ胎内で活発かどうかは生まれてくる赤ん坊の性別に影響しません」と返されてしまった。
本当はこういう話もゆっくり夫としたいのだが、王都に戻ってきてから彼はずっと忙しく働きまわっていてろくに屋敷にも帰ってきていない。最近はたまにリナレーアのいる部屋に顔を出してくれたりするのだが、ディートリンデが間に入ってきてまともに会話もできないうちに仕事に戻ってしまうのだ。
姉がずっと側にいてくれることが心強いのは確かだが、気詰まりに感じるのも本当であった。
(少し前まで、ザイラス達と旅をしながら四六時中一緒にいたのが夢のようだわ)
リナレーアはもう一度息を吐いた。
すると背後からふわりと抱きしめられて、覚えのある温もりが耳元に押し付けられた。
「リィナ」
少し低く甘い声。
リナレーアは一瞬呼吸を止めた。
「あなた」
「ちょっとそのままじっとしてろ」
そう言われたので振り向こうとしたのをやめる。夫は背後からぎゅうぎゅうと妻を抱きしめ、子猫のようにその鼻先をすんと鳴らした。
やがて満足したのか、腕の力を緩めたザイラスがリナレーアの正面に回って膝をつき目線を合わせる。
久しぶりに間近に見た夫は一緒に旅をしていた時よりも少し痩せていたが、顔色は悪くなかった。
「お仕事を抜け出してこられたの?」
リナレーアはすっと手を伸ばすと夫のほおに触れた。すると彼はそちらに顔を傾けて、漆黒の瞳でじっと妻を見つめる。
「今日はもう終わりだ。ずっとお前と一緒にいる」
「え?」
リナレーアは目をぱちくりとさせた。
「邪魔者もいなくなっただろう? 今日は夜まで二人きりだ」
「まぁ……あなた、もしかして」
ヘンリック王がディートリンデをさらっていってしまったのを頭に思い浮かべる。あれはザイラスの差し金だったのだろうか。
「クソ王もいい加減王妃を決めろとせっつかれてるんだ。いい機会だから無理やり王妃にするなりきっぱり振られるなりしてこいと言っておいた」
「まぁ……」
「リィナ、立てるか? こっちにおいで」
立ち上がったザイラスに腕を引かれ、リナレーアは部屋の隅に置かれた長椅子の方へ歩いた。すると先にザイラスが腰掛け、その脚の間に座れとばかりにぽんぽんと座面を叩かれる。
リナレーアは少し躊躇したが、断るのもおかしいのでどきどきしながらちょこんとそこに腰掛けた。すると待ってましたとばかりに背後から腕が回される。ザイラスは身をかがめてリナレーアの肩に自分の顎を置いた。その手は大きくなった妻の腹を撫でている。
「動くか?」
「……はい、とても元気な子ですよ」
久々の甘い雰囲気に、リナレーアはどきどきするのが抑えられない。顔が赤くなっているのが彼に見つからなければいいと心の中で願った。
ザイラスはその手をリナレーアの腹にあてて少し待ったが、やがて不満そうに言った。
「動かないじゃないか」
「今はきっと寝ているんだわ」
リナレーアはくすりと笑った。
お腹の子が動くのを夫にも見せてあげたい。たまにだがはっきりと、これは足なのだろうなとわかる時があるのだ。この中には本当に、自分たちの赤ん坊が宿っている。
しかしザイラスの切り替えは早かった。
「そうか、それは好都合だ」
そう言ったかと思うと、ぐいとリナレーアの顎を掴んで口付ける。突然のそれにもちろん抵抗などしなかったが、やがて口づけが深くなっていくとリナレーアは混乱した。
唇が離れた時、リナレーアは夫と自分の持つ温度が同じになっているのを感じたし、それが恥ずかしくて彼の顔を見られなかった。
「……恥かしいわ」
突然のキスに準備のできていなかった心臓が飛び出しそうだ。こんなのは、胎児にもよくないに違いない。
「ヤドリギ、というのを知っているか?」
しかしザイラスはリナレーアの言葉など聞いていない様子で言った。
「他の樹に寄生して生えてくる灌木だそうだ。西の方の国にはこの時期クリスマスという祭りがあって、その祭りの日に、ヤドリギの下に立っている相手にはキスをしてもいいということになっているらしい」
「くりすます、ですか……」
なんの話かわからない。そっと顔を上げて夫を見ると、彼の眼差しは触れたら火傷をしてしまいそうな熱を帯びていた。
「数週間前その話を聞いた時は、この屋敷の中を毎日クリスマスということにしてお前の部屋の天井にくまなくヤドリギを敷き詰めれば、たとえそこに姉君がいようが関係なくお前にキスできるのかと思った」
「……そんなこと、なさいませんよね?」
「それくらい、お前が足りなかった」
ザイラスが再び強くリナレーアを抱きしめる。
その力の強さと耳元で漏れたため息に、彼も自分と同じくらい寂しかったのだと感じられてリナレーアは切なくなった。夫の腕に自らの手を絡め、顔を夫にすり寄せる。
「わたくしもです。ずっとこうしてゆっくりとお話したかった」
「俺はお前に触りたかった」
そう言いながら夫の手が妻の胸のふくらみに伸びてきた時、リナレーアの腹をぽこんと蹴った者がいた。
「あ! あなた! 今赤ちゃんが蹴ったわ!」
リナレーアはそれまでの色っぽい雰囲気を霧散させる声を上げた。
「ほら! 触ってみてください!」
不埒な行為に及ぼうとしていた夫の手を掴んで自らの腹に当てさせる。すると今度は胎児がぐいーと母の腹を押した。
「ね? わかりました?」
「……」
振り向けば、夫が今まで見たことのないような顔で妻の腹を覗き込んでいる。
「どうです? 元気な子でしょう?」
「……」
するとザイラスはすっかり毒気の抜けた様子で息を吐くと、背もたれに体重を預けて天井を仰いだ。
「あなた?」
どうしたのかと心配になって体勢を変え夫に向き直ったリナレーアは、困ったように笑う彼を見てどきりと胸を高鳴らせた。彼が演技でなくこんなふうに優しく笑うことはあまりないのだ。
「まったく、お前には敵わないなリィナ」
なんのことを言われているかわからない。けれどザイラスは、今度は柔らかく妻を抱きしめると、「俺がいなかった間のことを教えてくれ。久しぶりにゆっくり話そう」と言った。
そしてそれは、リナレーアがずっと望んでいたことなのだった。
——この五日ほど後、レイデ夫人は元気な男児を出産した。
その男児はゲイル=レイデと名付けられ、多くの祝福を受けた。