可愛い可愛い小さな妹
Open Menu
魔物解放団の一件が終わり冒険の旅に出たレイデ夫妻とその一行がエンブリー伯爵領に寄ったのは、リナレーアの療養中、回復したら一度領地に戻ってきてほしいと長兄アロイスから再三の懇願があったからだ。
しかし伯爵領の屋敷に戻ってみると、残念ながら領主夫妻は領地視察に出ていて留守、謹慎中である次兄ヴァルターは山奥の別宅に滞在、アロイスの妻は実家に帰省中ということで、迎えたのは長兄アロイスと長姉ディートリンデだけであった。
「ほらリナレーア。これも食べなさい。こっちも。お前の好物ばかり用意したからな。きちんと食べないとまた傷が開いてしまうぞ。ただでさえ誰かさんのおかげで心労が絶えない生活をしているのだろうからな」
「そうよ。誰かさんが姿を消していたせいでひどい怪我をしたのだから、きちんと養生して治さないといけないのに。あてもない旅だなんて。私が側にいたら絶対に許さなかったわよ」
目の前の皿に、兄と姉がひょいひょいと食べ物を山盛りにしていくのを見て、リナレーアは苦笑した。
アロイスとディートリンデのいう「誰かさん」が誰のことかは聞かなくてもわかる。これは自分の隣で黙々と食事をするザイラスへの当てこすりだ。
リナレーアはザイラスが気分を害しているのではとちらりと伺ったが、妻の視線に気づいた彼は冗談ぽく眉を上げてみせただけだった。
そもそもリナレーアが一度実家に戻ると言った時に、彼はこの状況を予想していたのかもしれない。それでも嫌な顔一つ見せなかったのは、リナレーアの気持ちを考えてに違いなかった。
「ありがとう、アロイスお兄様、ディートリンデお姉様。でもわたくしの怪我はもうすっかり治ったのよ。なんなら証拠にこの食卓の周りを駆け回ってさしあげましょうか?」
リナレーアはにっこりと微笑んで言った。
しかしさすがアロイスは、リナレーアのその笑顔にごまかされたりなんてしなかった。
「お前はいつも無茶をする。そのお前の無茶を歓迎している人間なんてお前の周りには一人もいないと自覚してくれよ」
「同感ですね、アロイス様」
ザイラスが言った。
「リナレーアはあまりに向こう見ずで、考えなしだ」
彼はそう非難するようなことを口にしてから、とろけるような眼差しでリナレーアを見てその背に腕を回した。
「でもだからこそ目が離せないのですよ」
「まぁ、ザイラスったら」
どうやら彼は、アロイスの前ではレイデ伯爵の仮面を被り通すつもりらしい。久しぶりの紳士的な夫の登場に、リナレーアはどぎまぎした。
頬を染めて夫を見つめていたリナレーアは、上座に座るアロイスが青ざめぷるぷるとワイングラスを持つ手を震わせていることに気づかなかった。ディートリンデもまた、苛立ちを隠せない様子で眉間にしわを寄せる。
「リナレーア!」
アロイスはぐいとワインを飲み干すと、必要以上に大きな声で言った。
驚いた顔で夫から兄に視線を移した妹に、ぎこちない笑顔を向ける。
「……料理が冷めてしまうから食べなさい」
兄はもっと他に言いたいことがあったのを飲み込んだ様子であったが、リナレーアは「ええ、ありがとうアロイスお兄様」と言ってフォークとナイフを手に取った。
目の前に並ぶ料理は、先ほどアロイスが言っていた通りリナレーアの好物ばかりだ。エンブリー領を流れるキャベゼ川でとれるイタという魚のムニエルに、玉ねぎの入ったタルタルソース。甘辛く味付けしたじゃがいもと、卵たっぷりのキッシュ、領内の牛から絞った牛乳を使ったシチュー。エイダ達も厨房でこれを食べているはずだ。
まずはタルタルソースをからめたムニエルから。上品に切り分けてから口に運ぶと、玉ねぎのシャキシャキとした食感とふんわりとしたムニエルの食感が合わさり、香草のたっぷり使われたその複雑な味付けにリナレーアは思わず顔をほころばせた。
「ああ、美味しいわ」
「料理長が張り切って作っていたからな。皆お前が帰ってきてくれて嬉しいんだよ」
「そうだわ、リナレーア。うちにはいつまでいるつもり? もちろんお父様達がお戻りになるまでいるんでしょう?」
リナレーアはもぐもぐと口の中のものを咀嚼し飲み込んでから答えた。
「それがね、ザイラスと相談して、ヴァルターお兄様やお父様達がいらっしゃる町にも寄っていけばいいっていうことになったのよ。だからそうね、明後日には発つわ」
「明後日!」
アロイスは悲鳴のような声を上げた。
「それはいくらなんでも急ぎすぎだろう。少なくとも一月は滞在するものだとばかり思っていたのに」
「だって、いつまでこうして自由に旅をしていられるかわからないでしょう? わたくし、なるべくいろいろなものを見たいのよ。ね、お兄様」
「だがな、リナレーア」
「ご心配なく、アロイス様」
気色ばんで言い募ろうとしたアロイスをザイラスが遮った。
「妻は私が護りますので」
リナレーアからしてみればこれ以上信用できる言葉はないというのに、アロイスは苦虫を噛み潰したような顔になってザイラスを睨んだ。
ディートリンデがふんと鼻を鳴らす。
「よく言うわね。リナレーアにあんな大怪我をさせたくせに」
「お姉様」
リナレーアは姉の言葉に眉宇を寄せたが、彼女が何か反論する前にアロイスががたりと立ち上がった。
「レイデ伯爵」
エンブリー伯爵家の嫡男は、ナプキンで口を拭いてから冷ややかな視線で義理の弟を見下ろす。
「ちょっとこっちへ来たまえ」
「お兄様」
いったい何をするつもりかとリナレーアは腰を浮かしかけたが、隣のザイラスに止められる。
「大丈夫。君はここにいて」
紳士モードの夫にそう囁かれては、大人しく座っているほかないリナレーアである。
連れ立って食堂から出て行った兄と夫を見送って、リナレーアは珍しく途方にくれたような顔をした。
「お兄様ったら。あまりザイラスをいじめないでほしいのに」
「いじめさせてあげなさいよ」
ディートリンデはつんとした顔でキッシュにナイフを入れながら言った。
「言っておくけれど、ザイラス=レイデに対する私とアロイスお兄様の評価は今最低よ。どこで何をやっていたか知らないけれど、リナレーアにあんな怪我をさせて、その上二月も放置して。出会い頭に殴られなかっただけ感謝してもらいたいものだわ」
「お姉様」
「そんな目をして私を見ても無駄です」
甘えるような妹の視線に、姉は断固とした態度で答えた。
「あの男は、一度がつんとやられるべきなのよ。少なくとも、私たちエンブリー家の人間にはその権利があるわ」
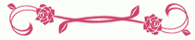
——本当なら、このザイラス=レイデという男を出会い頭に一発殴ってやりたかったアロイスである。
けれどディートリンデに、そんなことをすればリナレーアがもう帰ってこないかもしれないと言われてかろうじて我慢した。
リナレーアが大けがをしたと聞いて飛んで行きたかったのに、領地を空にするわけにはいかないからという理由で残留を余儀なくされた時はおかしくなるかと思った。リナレーアの様子を知りたくて、毎日手紙を送った。
すべて、この男のせいだ。
ザイラス=レイデ。
リナレーアは腕を脱臼、骨折し、爪は剥がれていたという。背中には傷さえ残っているはずだ。
可愛い可愛い小さなリナレーア。
自分が側にいたなら、あの子をそんな目に遭わせなかったのに。
「——君は、リナレーアの手料理を食べたことがあるかい? 肉料理や魚料理、スープなどをあの子が作っているのを見たことは?」
食堂を出て、隣の談話室でザイラスと二人きりになったアロイスは、まっすぐにザイラスを見据えてそう切り出した。
「……ありません」
怪訝そうな顔でそう答えたザイラスに、アロイスは優越感で鼻を膨らませる。
「私はある」
これは、ディートリンデにもアロイスがたびたび自慢することの一つであった。
「リナレーアが七歳の時のことだ。あの子は、私の誕生日に、初めて自らの手料理を振舞ってくれた。なぜか。もちろん、あの子にとって私が大切な兄だからだ。残念ながらあの子がスープの隠し味として入れた香草の中に毒草が紛れていて、私は三日三晩生死をさまよったがね……あれは私の人生の中でも最高の食事であった」
「……」
「しかしあれ以降リナレーアは料理をするのをやめた。自分の作ったもので私が死にかけたのがよほど堪えたらしい。回復した私が何度言っても、あの子はもう料理を作ろうとはしなかった」
リナレーアは優しい子である。
大切な兄が苦しむ姿をもう見たくなかったのだろう。
「だが、しかし!」
アロイスはかっと目を見開いて声を上げた。
「そのあの子が! 君のために焼き菓子を焼いたというじゃないか!」
「……はぁ」
「――羨ましい!! じゃなくて、そのことの重大さが君にはわかっているのか!!」
アロイスの口から思わず本音がぽろりしたが、彼にはそんなこと押して流してしまえるほどの強い感情があった。
「自分の作ったもので兄が死にかけたことはあの子にとってトラウマだった。それを乗り越えてでも、あの子は何度も君に焼き菓子を作り君が迎えにきてくれるのを待っていたというじゃないか! 二月もの間!」
帰ってきたディートリンデからそれらの経緯を聞かされた時、アロイスは心からリナレーアの結婚を止めなかったことを後悔したし、できるならザイラス=レイデを見つけ出して八つ裂きにしてやりたいとさえ思った。
「一億歩譲って、あの子が怪我をしてしまったことは横に置いておこう。何はともあれ、命に別状はなかったのだから。それにしてもなぜ! すぐにリナレーアを迎えに行かなかった! 怪我をしたあの子の側にいてやらなかったんだ!」
実際のところ、アロイスがもっとも腹を立てていたのはそこであった。
誰かを完璧に護りきることは難しい。十二年前のヴァルターとリナレーアが遭遇した悲劇にしてもそうだ。アロイスがどんなにすべての悲しみから家族を護りたいと思っていても、そうできないことはある。
だからこそことが起こった後に、何ができるかが問題なのではないか。
「あの子は君を待っていた。君が出した離婚申し立て書を父に破り捨てさせ、怪我に苦しみながらも君を待っていたんだぞ!」
「——知っています」
ザイラスは答えた。
「リナレーアが、私にだけわかるように場所を指定してきたのに気づいてすぐ、私はあの場所にいって彼女を見ていましたから」
(見ていただと?)
アロイスは唖然として次ぐ言葉を失った。自分のことを待つリナレーアを、姿を現さずに見ていたというのか。
「……リナレーアは、稀有な女性だ」
ザイラス=レイデはまっすぐにアロイスを見返していた。
ディートリンデが言っていた。
『あれは、一筋縄ではいかない男よ』
なぜだか今あの言葉が蘇る。目の前の、自分よりも年若い男の双眸には老成した光が宿っていた。
「彼女に私は救われました。リナレーアに出会って世界が変わった。彼女は私にとって無二の存在で、決して失えない人になった」
いつもなら『そんなのは、私にとっても同じだ』と対抗心むき出しの発言をしていたであろうアロイスであるが、今回ばかりはザイラスの雰囲気に気圧されてなにも言えなかった。
「だから恐ろしくなったんです。彼女はあまりに自由で、羽が生えているようにどこへでも飛んでいきそうだったから。私は、彼女を永遠に失ってしなう前に、彼女から逃げた」
リナレーアは随分と長い間恐怖という感情を失っていたらしいが、そうでなくてもあの子は好奇心旺盛でどんなことでもとにかくやってみる、というところのある子であった。冒険に憧れ、見知らぬ世界に憧れた。
「でも彼女は、俺から自由になってもどこかへ飛んでいったりしなかった」
(『俺』?)
その一人称の変化にアロイスは違和感を覚えたが、眉を上げるだけにとどめた。
「臆病者の俺が戻ってくるのを待っていてくれた。それは彼女が——リナレーアが、俺を愛してくれているからです」
『実はわたくし、夫に恋をしたのです』
かつて、リナレーアから送られてきた手紙にあったあの言葉。
あの子は、恋に落ちた。
おそらく生まれて初めての恋だ。リナレーアにはかつて恋人がいたが、あれはまるでままごとのようなものであった。
「そのことに気づくのに随分と時間がかかりました。そのせいで、アロイス様には心労をおかけしてしまったことをお詫びします」
そう言って、ザイラスが頭を下げる。
リナレーアがいたら目を丸くして驚いただろう。アロイスは知らないが、ザイラスが誰かに頭を下げるなど、今までにないことであった。
「これだけはお約束します。今まであなた方がそうしてこられたように、これからは俺がリナレーアを護ります。俺の持つすべてをかけて」
アロイスはもうたまらなかった。
ばっとザイラスに背を向けて、「ふん。わかったならもういい。先に食堂に戻ってくれ!」と突き放すように言った。
「失礼いたします」
最後まで礼儀を守って談話室を辞したザイラスが扉を閉めた音を聞いた後、アロイスはその場に崩れ落ちて我慢していた涙をぼたぼたと流した。
隣の食堂に泣き声が聞こえているかもしれないと思いながらも、アロイスはもう堪えきれなかった。大切な、可愛い小さなリナレーアが家族以外の男のものになったのだと痛感して、おいおいと声を上げ目が腫れるまで泣いたのだった。
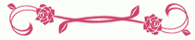
「……アロイスお兄様。きっとわたくしがまたお嫁にいってしまうような気持ちになったのね」
歓待の晩餐を終え部屋に戻ったリナレーアは、食堂にまで響いてきたこちらの哀れを誘う兄の泣き声を思い出して息を吐いた。
「いや、泣きすぎじゃねぇ?」
兄と夫がどんなことを話したのか具体的には教えてもらえなかったが、とにかくザイラスが『リナレーアは俺に任せてください』みたいなことを言ったらアロイスはあんなかんじになってしまったらしい。
寝台に腰掛けてタイを取り、シャツのボタンをいくらか外したザイラスは、大きく息を吐いた。疲れた様子の夫の隣に寄り添い、リナレーアは「ありがとうございます」と礼を言う。
ザイラスが、とても頑張ってくれたことは疑いようもなかった。
「リィナ」
「なあに?」
「あんたが、昔兄貴を殺しかけたせいで料理を作らなくなったっていうのは本当か?」
「え?」
リナレーアは二度瞬きをした。
「お兄様を殺しかけた?」
眉を寄せて小鳥のように首をかしげる。記憶を辿ったリナレーアは、「ああ」と言って両手を叩いた。
「そうね。そんなこともあった気がするわ。お兄様がずっと寝込んでいらして、とても心配だったのよ。でも料理をしない理由はべつにそれじゃないわ。だって、わたくしが何か作るよりもベティみたいな専門の方が作った方がずっと美味しくできるでしょう? だから料理にはあまり興味が持てなかったのだけれど……どうして?」
「……いや」
ザイラスは少し呆れた様子でリナレーアを見てから、ついばむようにキスをした。
「俺が食べたいと言ったら、俺のために何か作ってくれるか?」
そういえば以前も一度、そんなようなことを言われた気がする。
リナレーアはにっこりと笑って答えた。
「あなたが望むのならもちろんよ。でも味の保証はしませんからね」
しかし伯爵領の屋敷に戻ってみると、残念ながら領主夫妻は領地視察に出ていて留守、謹慎中である次兄ヴァルターは山奥の別宅に滞在、アロイスの妻は実家に帰省中ということで、迎えたのは長兄アロイスと長姉ディートリンデだけであった。
「ほらリナレーア。これも食べなさい。こっちも。お前の好物ばかり用意したからな。きちんと食べないとまた傷が開いてしまうぞ。ただでさえ誰かさんのおかげで心労が絶えない生活をしているのだろうからな」
「そうよ。誰かさんが姿を消していたせいでひどい怪我をしたのだから、きちんと養生して治さないといけないのに。あてもない旅だなんて。私が側にいたら絶対に許さなかったわよ」
目の前の皿に、兄と姉がひょいひょいと食べ物を山盛りにしていくのを見て、リナレーアは苦笑した。
アロイスとディートリンデのいう「誰かさん」が誰のことかは聞かなくてもわかる。これは自分の隣で黙々と食事をするザイラスへの当てこすりだ。
リナレーアはザイラスが気分を害しているのではとちらりと伺ったが、妻の視線に気づいた彼は冗談ぽく眉を上げてみせただけだった。
そもそもリナレーアが一度実家に戻ると言った時に、彼はこの状況を予想していたのかもしれない。それでも嫌な顔一つ見せなかったのは、リナレーアの気持ちを考えてに違いなかった。
「ありがとう、アロイスお兄様、ディートリンデお姉様。でもわたくしの怪我はもうすっかり治ったのよ。なんなら証拠にこの食卓の周りを駆け回ってさしあげましょうか?」
リナレーアはにっこりと微笑んで言った。
しかしさすがアロイスは、リナレーアのその笑顔にごまかされたりなんてしなかった。
「お前はいつも無茶をする。そのお前の無茶を歓迎している人間なんてお前の周りには一人もいないと自覚してくれよ」
「同感ですね、アロイス様」
ザイラスが言った。
「リナレーアはあまりに向こう見ずで、考えなしだ」
彼はそう非難するようなことを口にしてから、とろけるような眼差しでリナレーアを見てその背に腕を回した。
「でもだからこそ目が離せないのですよ」
「まぁ、ザイラスったら」
どうやら彼は、アロイスの前ではレイデ伯爵の仮面を被り通すつもりらしい。久しぶりの紳士的な夫の登場に、リナレーアはどぎまぎした。
頬を染めて夫を見つめていたリナレーアは、上座に座るアロイスが青ざめぷるぷるとワイングラスを持つ手を震わせていることに気づかなかった。ディートリンデもまた、苛立ちを隠せない様子で眉間にしわを寄せる。
「リナレーア!」
アロイスはぐいとワインを飲み干すと、必要以上に大きな声で言った。
驚いた顔で夫から兄に視線を移した妹に、ぎこちない笑顔を向ける。
「……料理が冷めてしまうから食べなさい」
兄はもっと他に言いたいことがあったのを飲み込んだ様子であったが、リナレーアは「ええ、ありがとうアロイスお兄様」と言ってフォークとナイフを手に取った。
目の前に並ぶ料理は、先ほどアロイスが言っていた通りリナレーアの好物ばかりだ。エンブリー領を流れるキャベゼ川でとれるイタという魚のムニエルに、玉ねぎの入ったタルタルソース。甘辛く味付けしたじゃがいもと、卵たっぷりのキッシュ、領内の牛から絞った牛乳を使ったシチュー。エイダ達も厨房でこれを食べているはずだ。
まずはタルタルソースをからめたムニエルから。上品に切り分けてから口に運ぶと、玉ねぎのシャキシャキとした食感とふんわりとしたムニエルの食感が合わさり、香草のたっぷり使われたその複雑な味付けにリナレーアは思わず顔をほころばせた。
「ああ、美味しいわ」
「料理長が張り切って作っていたからな。皆お前が帰ってきてくれて嬉しいんだよ」
「そうだわ、リナレーア。うちにはいつまでいるつもり? もちろんお父様達がお戻りになるまでいるんでしょう?」
リナレーアはもぐもぐと口の中のものを咀嚼し飲み込んでから答えた。
「それがね、ザイラスと相談して、ヴァルターお兄様やお父様達がいらっしゃる町にも寄っていけばいいっていうことになったのよ。だからそうね、明後日には発つわ」
「明後日!」
アロイスは悲鳴のような声を上げた。
「それはいくらなんでも急ぎすぎだろう。少なくとも一月は滞在するものだとばかり思っていたのに」
「だって、いつまでこうして自由に旅をしていられるかわからないでしょう? わたくし、なるべくいろいろなものを見たいのよ。ね、お兄様」
「だがな、リナレーア」
「ご心配なく、アロイス様」
気色ばんで言い募ろうとしたアロイスをザイラスが遮った。
「妻は私が護りますので」
リナレーアからしてみればこれ以上信用できる言葉はないというのに、アロイスは苦虫を噛み潰したような顔になってザイラスを睨んだ。
ディートリンデがふんと鼻を鳴らす。
「よく言うわね。リナレーアにあんな大怪我をさせたくせに」
「お姉様」
リナレーアは姉の言葉に眉宇を寄せたが、彼女が何か反論する前にアロイスががたりと立ち上がった。
「レイデ伯爵」
エンブリー伯爵家の嫡男は、ナプキンで口を拭いてから冷ややかな視線で義理の弟を見下ろす。
「ちょっとこっちへ来たまえ」
「お兄様」
いったい何をするつもりかとリナレーアは腰を浮かしかけたが、隣のザイラスに止められる。
「大丈夫。君はここにいて」
紳士モードの夫にそう囁かれては、大人しく座っているほかないリナレーアである。
連れ立って食堂から出て行った兄と夫を見送って、リナレーアは珍しく途方にくれたような顔をした。
「お兄様ったら。あまりザイラスをいじめないでほしいのに」
「いじめさせてあげなさいよ」
ディートリンデはつんとした顔でキッシュにナイフを入れながら言った。
「言っておくけれど、ザイラス=レイデに対する私とアロイスお兄様の評価は今最低よ。どこで何をやっていたか知らないけれど、リナレーアにあんな怪我をさせて、その上二月も放置して。出会い頭に殴られなかっただけ感謝してもらいたいものだわ」
「お姉様」
「そんな目をして私を見ても無駄です」
甘えるような妹の視線に、姉は断固とした態度で答えた。
「あの男は、一度がつんとやられるべきなのよ。少なくとも、私たちエンブリー家の人間にはその権利があるわ」
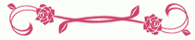
——本当なら、このザイラス=レイデという男を出会い頭に一発殴ってやりたかったアロイスである。
けれどディートリンデに、そんなことをすればリナレーアがもう帰ってこないかもしれないと言われてかろうじて我慢した。
リナレーアが大けがをしたと聞いて飛んで行きたかったのに、領地を空にするわけにはいかないからという理由で残留を余儀なくされた時はおかしくなるかと思った。リナレーアの様子を知りたくて、毎日手紙を送った。
すべて、この男のせいだ。
ザイラス=レイデ。
リナレーアは腕を脱臼、骨折し、爪は剥がれていたという。背中には傷さえ残っているはずだ。
可愛い可愛い小さなリナレーア。
自分が側にいたなら、あの子をそんな目に遭わせなかったのに。
「——君は、リナレーアの手料理を食べたことがあるかい? 肉料理や魚料理、スープなどをあの子が作っているのを見たことは?」
食堂を出て、隣の談話室でザイラスと二人きりになったアロイスは、まっすぐにザイラスを見据えてそう切り出した。
「……ありません」
怪訝そうな顔でそう答えたザイラスに、アロイスは優越感で鼻を膨らませる。
「私はある」
これは、ディートリンデにもアロイスがたびたび自慢することの一つであった。
「リナレーアが七歳の時のことだ。あの子は、私の誕生日に、初めて自らの手料理を振舞ってくれた。なぜか。もちろん、あの子にとって私が大切な兄だからだ。残念ながらあの子がスープの隠し味として入れた香草の中に毒草が紛れていて、私は三日三晩生死をさまよったがね……あれは私の人生の中でも最高の食事であった」
「……」
「しかしあれ以降リナレーアは料理をするのをやめた。自分の作ったもので私が死にかけたのがよほど堪えたらしい。回復した私が何度言っても、あの子はもう料理を作ろうとはしなかった」
リナレーアは優しい子である。
大切な兄が苦しむ姿をもう見たくなかったのだろう。
「だが、しかし!」
アロイスはかっと目を見開いて声を上げた。
「そのあの子が! 君のために焼き菓子を焼いたというじゃないか!」
「……はぁ」
「――羨ましい!! じゃなくて、そのことの重大さが君にはわかっているのか!!」
アロイスの口から思わず本音がぽろりしたが、彼にはそんなこと押して流してしまえるほどの強い感情があった。
「自分の作ったもので兄が死にかけたことはあの子にとってトラウマだった。それを乗り越えてでも、あの子は何度も君に焼き菓子を作り君が迎えにきてくれるのを待っていたというじゃないか! 二月もの間!」
帰ってきたディートリンデからそれらの経緯を聞かされた時、アロイスは心からリナレーアの結婚を止めなかったことを後悔したし、できるならザイラス=レイデを見つけ出して八つ裂きにしてやりたいとさえ思った。
「一億歩譲って、あの子が怪我をしてしまったことは横に置いておこう。何はともあれ、命に別状はなかったのだから。それにしてもなぜ! すぐにリナレーアを迎えに行かなかった! 怪我をしたあの子の側にいてやらなかったんだ!」
実際のところ、アロイスがもっとも腹を立てていたのはそこであった。
誰かを完璧に護りきることは難しい。十二年前のヴァルターとリナレーアが遭遇した悲劇にしてもそうだ。アロイスがどんなにすべての悲しみから家族を護りたいと思っていても、そうできないことはある。
だからこそことが起こった後に、何ができるかが問題なのではないか。
「あの子は君を待っていた。君が出した離婚申し立て書を父に破り捨てさせ、怪我に苦しみながらも君を待っていたんだぞ!」
「——知っています」
ザイラスは答えた。
「リナレーアが、私にだけわかるように場所を指定してきたのに気づいてすぐ、私はあの場所にいって彼女を見ていましたから」
(見ていただと?)
アロイスは唖然として次ぐ言葉を失った。自分のことを待つリナレーアを、姿を現さずに見ていたというのか。
「……リナレーアは、稀有な女性だ」
ザイラス=レイデはまっすぐにアロイスを見返していた。
ディートリンデが言っていた。
『あれは、一筋縄ではいかない男よ』
なぜだか今あの言葉が蘇る。目の前の、自分よりも年若い男の双眸には老成した光が宿っていた。
「彼女に私は救われました。リナレーアに出会って世界が変わった。彼女は私にとって無二の存在で、決して失えない人になった」
いつもなら『そんなのは、私にとっても同じだ』と対抗心むき出しの発言をしていたであろうアロイスであるが、今回ばかりはザイラスの雰囲気に気圧されてなにも言えなかった。
「だから恐ろしくなったんです。彼女はあまりに自由で、羽が生えているようにどこへでも飛んでいきそうだったから。私は、彼女を永遠に失ってしなう前に、彼女から逃げた」
リナレーアは随分と長い間恐怖という感情を失っていたらしいが、そうでなくてもあの子は好奇心旺盛でどんなことでもとにかくやってみる、というところのある子であった。冒険に憧れ、見知らぬ世界に憧れた。
「でも彼女は、俺から自由になってもどこかへ飛んでいったりしなかった」
(『俺』?)
その一人称の変化にアロイスは違和感を覚えたが、眉を上げるだけにとどめた。
「臆病者の俺が戻ってくるのを待っていてくれた。それは彼女が——リナレーアが、俺を愛してくれているからです」
『実はわたくし、夫に恋をしたのです』
かつて、リナレーアから送られてきた手紙にあったあの言葉。
あの子は、恋に落ちた。
おそらく生まれて初めての恋だ。リナレーアにはかつて恋人がいたが、あれはまるでままごとのようなものであった。
「そのことに気づくのに随分と時間がかかりました。そのせいで、アロイス様には心労をおかけしてしまったことをお詫びします」
そう言って、ザイラスが頭を下げる。
リナレーアがいたら目を丸くして驚いただろう。アロイスは知らないが、ザイラスが誰かに頭を下げるなど、今までにないことであった。
「これだけはお約束します。今まであなた方がそうしてこられたように、これからは俺がリナレーアを護ります。俺の持つすべてをかけて」
アロイスはもうたまらなかった。
ばっとザイラスに背を向けて、「ふん。わかったならもういい。先に食堂に戻ってくれ!」と突き放すように言った。
「失礼いたします」
最後まで礼儀を守って談話室を辞したザイラスが扉を閉めた音を聞いた後、アロイスはその場に崩れ落ちて我慢していた涙をぼたぼたと流した。
隣の食堂に泣き声が聞こえているかもしれないと思いながらも、アロイスはもう堪えきれなかった。大切な、可愛い小さなリナレーアが家族以外の男のものになったのだと痛感して、おいおいと声を上げ目が腫れるまで泣いたのだった。
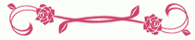
「……アロイスお兄様。きっとわたくしがまたお嫁にいってしまうような気持ちになったのね」
歓待の晩餐を終え部屋に戻ったリナレーアは、食堂にまで響いてきたこちらの哀れを誘う兄の泣き声を思い出して息を吐いた。
「いや、泣きすぎじゃねぇ?」
兄と夫がどんなことを話したのか具体的には教えてもらえなかったが、とにかくザイラスが『リナレーアは俺に任せてください』みたいなことを言ったらアロイスはあんなかんじになってしまったらしい。
寝台に腰掛けてタイを取り、シャツのボタンをいくらか外したザイラスは、大きく息を吐いた。疲れた様子の夫の隣に寄り添い、リナレーアは「ありがとうございます」と礼を言う。
ザイラスが、とても頑張ってくれたことは疑いようもなかった。
「リィナ」
「なあに?」
「あんたが、昔兄貴を殺しかけたせいで料理を作らなくなったっていうのは本当か?」
「え?」
リナレーアは二度瞬きをした。
「お兄様を殺しかけた?」
眉を寄せて小鳥のように首をかしげる。記憶を辿ったリナレーアは、「ああ」と言って両手を叩いた。
「そうね。そんなこともあった気がするわ。お兄様がずっと寝込んでいらして、とても心配だったのよ。でも料理をしない理由はべつにそれじゃないわ。だって、わたくしが何か作るよりもベティみたいな専門の方が作った方がずっと美味しくできるでしょう? だから料理にはあまり興味が持てなかったのだけれど……どうして?」
「……いや」
ザイラスは少し呆れた様子でリナレーアを見てから、ついばむようにキスをした。
「俺が食べたいと言ったら、俺のために何か作ってくれるか?」
そういえば以前も一度、そんなようなことを言われた気がする。
リナレーアはにっこりと笑って答えた。
「あなたが望むのならもちろんよ。でも味の保証はしませんからね」