花束を君に
Open Menu
社交界で人気のレイデ伯爵家にはよくいろいろなところから贈り物が届く。菓子やお酒、宝飾品や布など、そのすべてを管理して主人に報告し、返礼品を用意するのはすべて執事であるマーティンの仕事であった。
さてこの時、マーティンは悩んでいた。
伯爵家の屋敷の、贈答品を管理する一室。その壁際の小さな丸テーブルの上に置かれているのは一つの花束である。
ピンクの薔薇を基調に、豪奢に作られたその花束には特別な思いがこもっていることがうかがい知れる。添えつけられたメッセージカードには几帳面な字が書かれていて、マーティンはもう小一時間そのメッセージカードを睨みつけていた。
「困りましたね」
本来なら、贈り物はすべて主人に報告しなければいかないのだが、この花束とカードに限っては主人に報告すれば一波乱起きることが明白だった。
屋敷に戻ってきたリナレーア=レイデ伯爵夫人が第一子を産み落としてから数月、今、レイデ伯爵家はこの上なく幸福な雰囲気の中平穏を保っている。わざわざこんな波乱の元を投下して屋敷の中の空気を壊す必要はないのではとマーティンは思うのであった。
「しかし、かといって捨てるわけにもいかないですからね……」
「何を捨てるだって?」
うむむと唸ったマーティンは、不覚にもすぐ後ろまで近づいてきていた人物に気づかなかった。振り向けば、マーティンの主人にして魔物使いである、ザイラス=レイデが立っている。
「おや、旦那様。どうかされましたか?」
しかしマーティンは見苦しく動揺したりしなかった。にっこりと笑顔を浮かべて、問題のカードをさっと後ろ手に自らの袖の下に隠す。
花束だけならどうとでもいいわけはできる。問題はこのカードなのだ。いずれザイラスに報告するにしても、まずは女主人であるリナレーアに判断を仰いだ方がいいだろう。マーティンはそう判断して今はカードをザイラスから隠し通すことにしたが——いかんせん相手が悪かった。
「今袖に隠したものを出すか、三つ頭に食い殺されるかどちらか選ばせてやる」
ザイラスは少し目を細めて告げた。
「……」
レイデ家の優秀な執事は一拍の間を置いてため息をつく。
彼の主人がこういう時に冗談など言う性格ではないことを、マーティンはよく承知していた。
「今朝届いたものでございます」
マーティンはもうどうとでもなれ、という気持ちでカードを主人に差し出した。
受け取りさっとカードの内容に目を通したザイラスは、ちらりとマーティンの背後に置いてある花束を見て眉を上げる。マーティンは、室内の温度がいくらか下がったような気がした。
「それは燃やしておけ」
ザイラスはそう言い捨てると、踵を返して部屋を出て行った。その背中を無力感とともに見つめながら、どうかあまり大ごとになりませんようにと願うマーティンなのであった。
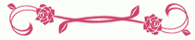
ベッドの中ですやすやと眠る息子を見つめる世界で一番可愛い妻の姿を部屋の中に認めてさえ、ザイラスの苛立ちは和らがなかった。それどころか、なぜかさらに怒りが燃え上がる。
彼はすでに一度くしゃくしゃに握りつぶしてしまったメッセージカードを、「あら、あなた」とこちらを見て微笑んだ妻の膝に放り投げた。
「これはなんだ」
「なんですか? これ」
リナレーアは聞かれたことをそのまま聞き返した。放り投げられたゴミのようなものを手にとり丁寧に広げる。逆さまになっていたのであろうそれを、一度首を傾げてから正位置に戻すその仕草も可愛らしい。
「あら、まぁ。懐かしい方ね」
リナレーアはにっこりと笑った。
その笑顔がまたとんでもなく愛らしいので、ザイラスはぎりりと拳を握りしめる。
マーティンが隠していたメッセージカードにはこう書かれていた。
リナレーア。
突然のカードに驚いているだろうか。
君が母になったと聞いて、どうしてもお祝いを贈りたくなったんだ。
幼い僕たちの恋と同じように可愛いらしいこの花を、気に入ってくれるとよいのだが。
あの時僕たちは違う道を行くと決めたけど、あの頃の幸福な時間はずっと僕の宝物だよ。
どうか幸せに。
ルイ
とんでもないことである。
(……恋、だと!)
ザイラスはその場で暴れ出したい衝動をかろうじて堪えていた。
この、宇宙で一番可愛い自分の妻に対して、「僕たちの恋」などという文言を送ってくる輩がいるなんて。
「花はどこにあるの?」
「マーティンに燃やすよう命じた」
「あら、まぁ」
リナレーアは目を丸くした。ザイラスの愛らしい妻は、ようやく夫の怒りに気づいたようだ。彼女は立ち上がり、すすと夫に歩み寄って腕に触れた。
「怒っていらっしゃるの?」
「男の素性を教えろ。そいつも燃やしにいく」
「まぁ、ザイラス」
リナレーアはちらりと背後に控えていたエイダに目配せをする。優秀な使用人はそれだけで察して一礼し、黙ったまま部屋を出て行った。
ベッドの中の赤ん坊——ゲイルはよく眠っている。息子の名前を決めたのはリナレーアだ。かつて自らの頭の中を食べた魔物の名前を息子につける妻の心中は計りかねたが、ザイラスを想ってのことであるはずだった。
「燃やしにいくだなんて」
「リナレーア、俺は自分の妻にちょっかいを出してくる男を放っておけるほど寛容じゃない」
「昔の話よザイラス。ルイは、私が十四くらいの時に親しくしていた人なの」
「親しく?」
ぴくりと、ザイラスの眉が上がる。
彼は自分の左腕に触れていたリナレーアの手を取ると、それをぐいと口元に引き寄せた。
「親しくっていうのは、どれくらいだ?」
指先にかかる夫の息にリナレーアは思わず頰を染める。
「あのね、あなた……いた」
リナレーアは、指先にぴりと走った痛みに眉宇を寄せた。夫が指先を噛んだのだ、と遅れて気づいた様子で瞬きをする。
「そいつはあんたのどこに触れた? 指には? 肩? それとも……」
言いながら、ザイラスがリナレーアの肩に触れる。そしてその手がつつと首筋を伝い、リナレーア=レイデの可愛らしい唇で止まると、彼女の顔はりんごのように真っ赤になった。
可愛いリナレーア。
彼女に恋をした人間が自分一人であるはずがないとわかっている。今妻が愛しているのは自分一人だと断言できるのだが、過去に彼女が自分以外の誰かに対してこうして顔を赤くしていたかと思うと、ザイラスは到底冷静ではいられないのであった。
唇に触れていた指を素早く彼女の腰に回し、強く引き寄せる。
吐息がかかるほどの距離で大きなリナレーアの瞳を覗き込み、ザイラスは言った。
「……おかしくなりそうだ」
リナレーアが瞬きをして、その長い睫毛がザイラスの鼻先をくすぐる。
緊張した様子で身体を固くしていた彼女は、間もなく何を思ったか爪先立ちになりその唇をザイラスのそれに押し付けた。
今度驚くのはザイラスの方であった。
リナレーアの方から口づけをしてくれたことなど数えるほどしかない。彼女は先ほどザイラスが歯を立てた指先で反対に夫の手を掴むと、今度はそれを自分の方に引き寄せ心臓の上に当てた。リナレーアは笑う。
「わたくしのここに触れたのは、あなただけだわ」
そう言って、自然な仕草でこちらに身を寄せてきた妻の背に腕を回す。リナレーアを腕の中に抱きしめてようやく、ザイラスは息を吐いたのだった。もう爆発させるしかないと思われるほど膨張していた怒りもいつの間にか収縮している。
「あんたといると、自分が情けなく思えてくる」
そう言うと、リナレーアは腕の中でくすくすと笑った。
「情けなくなんてないわ。あなたはわたくしの世界で一番の人ですもの」
柔らかな妻の髪に頰を寄せてベッドの中の息子に目をやると、両手を上げて眠っているゲイルはびくりと全身を震わせた。こういった生理的な反射は、幼い赤ん坊特有のものらしい。
「よく眠ってるな」
ザイラスが言うと、ぱっと身体を離したリナレーアは笑顔を見せて「かわいらしいでしょう? あのね、やっぱり目元はあなたに似ていると思うのよ。でもエイダが、口元はわたくしに似ているって」と言った。
このまま子供の話に移行しそうな気配を感じたザイラスは、リナレーアの花のような唇を一度強く塞いで頰を撫でると、にやりと笑ったのだった。
「確かに、あんたの唇は赤ん坊の肌のように柔らかい」
そうするとリナレーアがまたぼっと顔を赤くしたので、ザイラスは今度こそ声を上げて笑ったのだった。
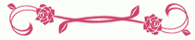
後日、ウルージ伯爵家の嫡男、ルイ=ウルージ子爵は自分の身に起きた恐ろしい出来事を友人に語って聞かせた。
曰く、ある夜、突然喉を圧迫されるような息苦しさを感じて目を覚ますと、目の前に六つの光る目があったのだという。
暗闇の中鼻につくような野生の獣の匂いがして、生暖かい吐息と獣の息遣いまで聞いた彼は、それが夢なのが現実なのかわからなかった。とにかくその巨大な獣に喉元を押さえつけられていると気づいた彼は恐慌をきたして助けを求めようとしたが、喉を押さえつけられているせいで声が出ない。どうしたわけか身体を動かすこともできずに、ウルージ子爵は自分はここで死ぬのかとさえ思った。
結果的に死ぬことはなく、その前に恐怖で気を失ってしまったウルージ子爵は、消えゆく意識の中で人間の男の声を聞いたのだった。
「夢でも見たんだろう」
友人が馬鹿にしたように言う。ウルージ子爵は憤慨して反論した。
「だがひどく現実的な夢だったんだ」
「ちなみに、その男はなんて言ったんだ」
「それが、これも奇妙な話なんだ」
男はこう言ったのだという。
——『リナレーア=レイデに二度と近づくな』
あの恐ろしい獣がかつての恋人となんの関係があるのかしれないが、もう二度とかつての恋人に花を贈ったりなどするまいと心に誓ったウルージ子爵なのであった。
さてこの時、マーティンは悩んでいた。
伯爵家の屋敷の、贈答品を管理する一室。その壁際の小さな丸テーブルの上に置かれているのは一つの花束である。
ピンクの薔薇を基調に、豪奢に作られたその花束には特別な思いがこもっていることがうかがい知れる。添えつけられたメッセージカードには几帳面な字が書かれていて、マーティンはもう小一時間そのメッセージカードを睨みつけていた。
「困りましたね」
本来なら、贈り物はすべて主人に報告しなければいかないのだが、この花束とカードに限っては主人に報告すれば一波乱起きることが明白だった。
屋敷に戻ってきたリナレーア=レイデ伯爵夫人が第一子を産み落としてから数月、今、レイデ伯爵家はこの上なく幸福な雰囲気の中平穏を保っている。わざわざこんな波乱の元を投下して屋敷の中の空気を壊す必要はないのではとマーティンは思うのであった。
「しかし、かといって捨てるわけにもいかないですからね……」
「何を捨てるだって?」
うむむと唸ったマーティンは、不覚にもすぐ後ろまで近づいてきていた人物に気づかなかった。振り向けば、マーティンの主人にして魔物使いである、ザイラス=レイデが立っている。
「おや、旦那様。どうかされましたか?」
しかしマーティンは見苦しく動揺したりしなかった。にっこりと笑顔を浮かべて、問題のカードをさっと後ろ手に自らの袖の下に隠す。
花束だけならどうとでもいいわけはできる。問題はこのカードなのだ。いずれザイラスに報告するにしても、まずは女主人であるリナレーアに判断を仰いだ方がいいだろう。マーティンはそう判断して今はカードをザイラスから隠し通すことにしたが——いかんせん相手が悪かった。
「今袖に隠したものを出すか、三つ頭に食い殺されるかどちらか選ばせてやる」
ザイラスは少し目を細めて告げた。
「……」
レイデ家の優秀な執事は一拍の間を置いてため息をつく。
彼の主人がこういう時に冗談など言う性格ではないことを、マーティンはよく承知していた。
「今朝届いたものでございます」
マーティンはもうどうとでもなれ、という気持ちでカードを主人に差し出した。
受け取りさっとカードの内容に目を通したザイラスは、ちらりとマーティンの背後に置いてある花束を見て眉を上げる。マーティンは、室内の温度がいくらか下がったような気がした。
「それは燃やしておけ」
ザイラスはそう言い捨てると、踵を返して部屋を出て行った。その背中を無力感とともに見つめながら、どうかあまり大ごとになりませんようにと願うマーティンなのであった。
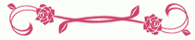
ベッドの中ですやすやと眠る息子を見つめる世界で一番可愛い妻の姿を部屋の中に認めてさえ、ザイラスの苛立ちは和らがなかった。それどころか、なぜかさらに怒りが燃え上がる。
彼はすでに一度くしゃくしゃに握りつぶしてしまったメッセージカードを、「あら、あなた」とこちらを見て微笑んだ妻の膝に放り投げた。
「これはなんだ」
「なんですか? これ」
リナレーアは聞かれたことをそのまま聞き返した。放り投げられたゴミのようなものを手にとり丁寧に広げる。逆さまになっていたのであろうそれを、一度首を傾げてから正位置に戻すその仕草も可愛らしい。
「あら、まぁ。懐かしい方ね」
リナレーアはにっこりと笑った。
その笑顔がまたとんでもなく愛らしいので、ザイラスはぎりりと拳を握りしめる。
マーティンが隠していたメッセージカードにはこう書かれていた。
リナレーア。
突然のカードに驚いているだろうか。
君が母になったと聞いて、どうしてもお祝いを贈りたくなったんだ。
幼い僕たちの恋と同じように可愛いらしいこの花を、気に入ってくれるとよいのだが。
あの時僕たちは違う道を行くと決めたけど、あの頃の幸福な時間はずっと僕の宝物だよ。
どうか幸せに。
ルイ
とんでもないことである。
(……恋、だと!)
ザイラスはその場で暴れ出したい衝動をかろうじて堪えていた。
この、宇宙で一番可愛い自分の妻に対して、「僕たちの恋」などという文言を送ってくる輩がいるなんて。
「花はどこにあるの?」
「マーティンに燃やすよう命じた」
「あら、まぁ」
リナレーアは目を丸くした。ザイラスの愛らしい妻は、ようやく夫の怒りに気づいたようだ。彼女は立ち上がり、すすと夫に歩み寄って腕に触れた。
「怒っていらっしゃるの?」
「男の素性を教えろ。そいつも燃やしにいく」
「まぁ、ザイラス」
リナレーアはちらりと背後に控えていたエイダに目配せをする。優秀な使用人はそれだけで察して一礼し、黙ったまま部屋を出て行った。
ベッドの中の赤ん坊——ゲイルはよく眠っている。息子の名前を決めたのはリナレーアだ。かつて自らの頭の中を食べた魔物の名前を息子につける妻の心中は計りかねたが、ザイラスを想ってのことであるはずだった。
「燃やしにいくだなんて」
「リナレーア、俺は自分の妻にちょっかいを出してくる男を放っておけるほど寛容じゃない」
「昔の話よザイラス。ルイは、私が十四くらいの時に親しくしていた人なの」
「親しく?」
ぴくりと、ザイラスの眉が上がる。
彼は自分の左腕に触れていたリナレーアの手を取ると、それをぐいと口元に引き寄せた。
「親しくっていうのは、どれくらいだ?」
指先にかかる夫の息にリナレーアは思わず頰を染める。
「あのね、あなた……いた」
リナレーアは、指先にぴりと走った痛みに眉宇を寄せた。夫が指先を噛んだのだ、と遅れて気づいた様子で瞬きをする。
「そいつはあんたのどこに触れた? 指には? 肩? それとも……」
言いながら、ザイラスがリナレーアの肩に触れる。そしてその手がつつと首筋を伝い、リナレーア=レイデの可愛らしい唇で止まると、彼女の顔はりんごのように真っ赤になった。
可愛いリナレーア。
彼女に恋をした人間が自分一人であるはずがないとわかっている。今妻が愛しているのは自分一人だと断言できるのだが、過去に彼女が自分以外の誰かに対してこうして顔を赤くしていたかと思うと、ザイラスは到底冷静ではいられないのであった。
唇に触れていた指を素早く彼女の腰に回し、強く引き寄せる。
吐息がかかるほどの距離で大きなリナレーアの瞳を覗き込み、ザイラスは言った。
「……おかしくなりそうだ」
リナレーアが瞬きをして、その長い睫毛がザイラスの鼻先をくすぐる。
緊張した様子で身体を固くしていた彼女は、間もなく何を思ったか爪先立ちになりその唇をザイラスのそれに押し付けた。
今度驚くのはザイラスの方であった。
リナレーアの方から口づけをしてくれたことなど数えるほどしかない。彼女は先ほどザイラスが歯を立てた指先で反対に夫の手を掴むと、今度はそれを自分の方に引き寄せ心臓の上に当てた。リナレーアは笑う。
「わたくしのここに触れたのは、あなただけだわ」
そう言って、自然な仕草でこちらに身を寄せてきた妻の背に腕を回す。リナレーアを腕の中に抱きしめてようやく、ザイラスは息を吐いたのだった。もう爆発させるしかないと思われるほど膨張していた怒りもいつの間にか収縮している。
「あんたといると、自分が情けなく思えてくる」
そう言うと、リナレーアは腕の中でくすくすと笑った。
「情けなくなんてないわ。あなたはわたくしの世界で一番の人ですもの」
柔らかな妻の髪に頰を寄せてベッドの中の息子に目をやると、両手を上げて眠っているゲイルはびくりと全身を震わせた。こういった生理的な反射は、幼い赤ん坊特有のものらしい。
「よく眠ってるな」
ザイラスが言うと、ぱっと身体を離したリナレーアは笑顔を見せて「かわいらしいでしょう? あのね、やっぱり目元はあなたに似ていると思うのよ。でもエイダが、口元はわたくしに似ているって」と言った。
このまま子供の話に移行しそうな気配を感じたザイラスは、リナレーアの花のような唇を一度強く塞いで頰を撫でると、にやりと笑ったのだった。
「確かに、あんたの唇は赤ん坊の肌のように柔らかい」
そうするとリナレーアがまたぼっと顔を赤くしたので、ザイラスは今度こそ声を上げて笑ったのだった。
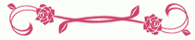
後日、ウルージ伯爵家の嫡男、ルイ=ウルージ子爵は自分の身に起きた恐ろしい出来事を友人に語って聞かせた。
曰く、ある夜、突然喉を圧迫されるような息苦しさを感じて目を覚ますと、目の前に六つの光る目があったのだという。
暗闇の中鼻につくような野生の獣の匂いがして、生暖かい吐息と獣の息遣いまで聞いた彼は、それが夢なのが現実なのかわからなかった。とにかくその巨大な獣に喉元を押さえつけられていると気づいた彼は恐慌をきたして助けを求めようとしたが、喉を押さえつけられているせいで声が出ない。どうしたわけか身体を動かすこともできずに、ウルージ子爵は自分はここで死ぬのかとさえ思った。
結果的に死ぬことはなく、その前に恐怖で気を失ってしまったウルージ子爵は、消えゆく意識の中で人間の男の声を聞いたのだった。
「夢でも見たんだろう」
友人が馬鹿にしたように言う。ウルージ子爵は憤慨して反論した。
「だがひどく現実的な夢だったんだ」
「ちなみに、その男はなんて言ったんだ」
「それが、これも奇妙な話なんだ」
男はこう言ったのだという。
——『リナレーア=レイデに二度と近づくな』
あの恐ろしい獣がかつての恋人となんの関係があるのかしれないが、もう二度とかつての恋人に花を贈ったりなどするまいと心に誓ったウルージ子爵なのであった。