死にかけ陛下の真実
Open Menu
オッリ=ベッカ座では気温と悲恋物の上演回数を比例させる、というのが暗黙の了解であった。ただでさえ寒い時期だ。せめて芝居だけでも心温まる演目を上演して客を呼び込もうというのである。
だからというわけではないが、レネ=オールストンは冬という季節が好きだった。
田舎では冬になれば雪が積もり、大人達は農作業もままならなくなるので家にこもって手仕事に精を出す。雪に覆われた外の世界は音がすべてあの白い平原に吸い込まれてしまったかのように静かで、天気の良い日に降り注ぐ光をきらきらと反射した。
都会に出てくると雪が降らないことに驚いたが、慣れてみるとこれはこれで悪くない。身を縮ませるような寒さの中歩いた後あたる暖炉の温もりは、幸福というものの象徴のようだ。大通りでは露店も数少なになっているが、外出している人はそう減っていない。彼らは早く暖炉にたどり着きたいというようにいそいそと歩き、暖かそうな灯りのともる家や酒場の中に吸い込まれていった。
いつもならそんな冬の雰囲気を楽しむところであるのだが、今のレネにはそうできない理由があった。
「……あのね、ついてこないでくれる?」
〈僕もこちらに用があるんだ〉
変態猥褻幽霊王がくっついて歩いてくるのだ。
しかも幽霊の状態で。
「あっそうじゃあ私あっちで別の用事済ませるから」
〈おっと偶然。僕もそちらでやることがあるんだった〉
しれっとした顔で幽霊王が方向転換したレネについてこようとしたその時、ぶちり、とレネの中で何かが切れた。
「あんた何か用事があるんじゃないわよねぇ! もーとっとと城に戻ってよ!」
〈残念ながらお前が一緒に城に戻って僕にキスしてくれないと誰も僕に気づかないから僕が寂しい〉
「知るか!」
レネとしては変態幽霊への正当な抗議であるのだが、いかんせん相手は幽霊。公共の場において、不利なのは彼女の方であった。
道ゆく人々が、虚空に向かって突然怒鳴り始めた彼女をざわざわと不審げな眼差しで見やる。それに気づいたレネ=オールストンは顔を真っ赤にして今度こそ幽霊王を無視すべくずんずんと歩き出したのだった。そして目当ての菓子店につくと乱暴に扉を開ける。
今日のオッリ=ベッカ座で行われる演目は、異国の『クリスマス』という祭りを題材にした『クリスマスの落し物』である。子供向けの作品なので子連れ客が多いのだが、例年子供客に配っていたお菓子を今年は用意し忘れたということで急遽レネが買い出しに出されたのである。
そこへ幽霊王が現れ、〈やぁレネ。僕と夜の散歩でもしないか?〉と言った時は気が遠くなった。
しかし彼女はどうにか、隣でじいとこちらを見つめてくる幽霊王を鋼鉄の意志で無視して必要な量の菓子を購入することに成功した。観客の子供に配る菓子の量はかなりのもので、店で借りた籠がいっぱいになったのでレネは誰かについてきてもらわなかったことを早々に後悔した。だが後の祭りである。大量の菓子を前にして立っているのはレネと使えない幽霊だけで、彼女は仕方なく一抱えもある籠を持って店を後にしたのだった。
〈大変そうだな。手伝いたいのは山々なのだが誰かさんがキスしてくれないから残念ながら僕は無力だ〉
〈こう寒いと人肌が恋しくなってくるな、そうだろう? 僕の寝台の隣はいつでもお前のためにあけてあるぞ〉
〈そういえば今夜の演目には出ないのか? またお前の珍妙な演技が見たいのに〉
などなど隣で世迷言を吐かれ続けてもレネはなんとか無視し続けたのだが、最後の台詞は無視できなかった。
〈去年のお前の『駒鳥の歌』での演技は見事だった〉
「見たの?」
思わず小声で問いかける。
するとヴィリオはにっこりと嬉しそうに笑ってから答えた。
〈ああ、台詞もない端役だったが、お前を見ていると空を飛んでいる駒鳥が本当に見えるようだった〉
それは褒め言葉のようにも聞こえたが、レネは眉を寄せた。
「嫌味なの?」
レネは、去年の『駒鳥の歌』では舞台上から落ちたのだ。空を飛ぶ駒鳥を目で追いかけるというだけの役だったのに、駒鳥を追いかけてふらふらと歩き出して舞台から落ちてしまった。幸い怪我はなかったものの、あの時も劇団長からこっぴどく叱られたものだ。
『駒鳥の歌』はレネにとって特別な演目だった。幼い頃、妖精の女王として舞台に立った。つまり初めて演じるということをした演目である。しかし今の彼女に大舞台で妖精の女王を演じる力量がないのは明らかで、去年は台詞のない一精霊の役に徹したのだった。
「王様が来てるなんて話聞かなかったけど」
〈お忍びだったからな。僕のことを敵対視してる人間が多すぎてうんざりしてたんだ。子供用の演目をやってる劇場なら見つかることもないだろうと思って逃げ込んだ〉
レネはぴたりと足を止めると、じっと幽霊王を見た。遠くでガラガラと馬車の走る音が聞こえる。
「もしかして、そこで私を見初めたとか?」
ヴィリオは以前からレネを知っているかのような口ぶりだった。けれどレネは会った覚えがない。舞台上での出会いならそれも理解できると思ったのだが、言ってすぐ馬鹿なことを口にしたと思った。
舞台から転げ落ちる間抜けな女優を見初める男がどこにいるというのだろう。
しかし王は笑って答えた。
〈そうかもな。お前という人間が気になり始めたのはそれが最初だ〉
騒がしかった馬車の音が近づいてきて、一度レネの横を通り過ぎたかと思うと急に停まった。そして中から見知った男性が飛び出してくる。
「オールストン嬢! そこにあの馬鹿はいないか!」
王の従者であるライナス=エレイン卿が『あの馬鹿』呼ばわりする相手はレネに知る限りただ一人である。
〈ライナスの奴、減俸だぞ〉
とヴィリオレイ王は苦々しく呟いたのだった。
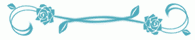
結局、レネは馬車に乗せられて王城に向かうことになった。
もちろん、死にかけている国王を救うためである。一度劇団に寄って菓子の籠を置いてきたが、ライナスが金のようなものを握らせると劇団長は嬉しそうに笑ってレネを見送った。
今現在、馬車の中はレネだけである。いや、正確にはレネと幽霊王がいた。
王を生き返らせる力を持つ《蘇らせる者》を捕獲したライナスは、突然王が死にかけてしまったことでやらなければならないことがたくさんあるあらしく、一足先に王城に戻っていってしまった。
〈ああせっかく密室で二人きりなのにお前に触れられないのが残念だ〉
「ねぇ、さっきの話だけど」
レネはヴィリオの口にした寝言をきっぱりと無視した。
「私を最初に認識したのが、前の冬よね? あんたが最初に死んだのはその冬の終わりでしょ? どうしてそんな短期間で、私があんたの《蘇らせる者》だってわかったの?」
『お前が僕を《蘇らせる者》だと知っていた』
そう言ったのはヴィリオ自身だ。レネにはずっと、あの台詞がひっかかっていた。自分とこの男にはどんな因縁があるというのだろう。
〈なんだ、そんなことを気にしていたのか〉
しかしヴィリオは破顔した。
「そりゃ気になるわよ。どういうわけなの? 教えなさいよ」
〈断る〉
笑顔のまま言下にそう言われ、レネは憤慨した。
「ちょっと」
しかし彼女の怒りはすぐにしぼんだ。ヴィリオが一呼吸の間に距離を詰め、レネを身動きできなくさせたからだ。
幽霊の彼には馬車の揺れでバランスを崩すことなどないらしい。ヴィリオはレネの正面に立ち、右膝を椅子に座る彼女の腿のすぐ横に置いて、左手はレネのすぐ後ろの壁に置いた。
相手が自分には触われないのだとわかってはいても、男性慣れしていないレネには危険信号が出る距離である。
肉体があったなら触れてしまいそうな距離でヴィリオが言った。
〈僕のことで悩むお前を見るのはたまらないよ。レネ=オールストン〉
(しまった。密室では、幽霊の方が有利だわ)
その時レネは大人しく馬車に乗ってしまったことを心から後悔したのだった。
触れられない幽霊相手では、突き飛ばして距離を取れないだけに狭い場所ではこちらの方が分が悪い。
赤くなった顔を今さら誤魔化すことはできないにしても、勝ったと思われたくないレネにはただ王を睨みつけることしかできないのだった。
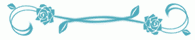
(まったく、これで無自覚なのだからタチが悪いな)
顔を赤くしたまま目を釣り上げられても、こちらとしては可愛いという感想しか出てこない。もし肉体があったならこのまま押し倒して屈服させて既成事実を作りたいところだが残念ながら彼はまだ幽霊なのであった。
ヴィリオレイ=レド=ネストルは心の中でため息をついた。
(ああ本当に、僕がこんな娘のためにいろいろと策略を巡らすはめになるとはね)
レネに言ったことは真実だ。
ヴィリオが彼女を認識したのは、去年の『駒鳥の歌』という演目が初めてであった。
見えない駒鳥を目だけで追う彼女の演技に驚いたのも確かだし、その後レネが舞台から落ちたことでその女優の顔は決定的にヴィリオの頭の中に記憶されることとなった。
城に戻って調べてみると、レネ=オールストンは売れない女優だった。
それからヴィリオはレネが出演する演目はなるべく見るようにしたが、どうにもその自分の情熱の理由を測りかねていた。
その理由というのが決定的になったのは、ヴィリオが暗殺されるひと月ほど前のことである。
彼はたまたま城を訪れていた宝石商から駒鳥のラペルピンを買った。それを目にして最初に思い浮かべたのがレネだったし、ヴィリオはレネの支援者になってもいいと思い始めていたので手始めにとそれをレネ=オールストン宛に贈ったのだ。
けれど、レネから礼の手紙が送られてくることはなかった。
ライナスの名を語ったので、相手が王だからと気後れしたわけではないはずだ。なら彼女は自分からの贈り物を無視したのかと思うと……ぞくぞくした。
ヴィリオレイ=レド=ネストルの嗜虐心に炎がついた瞬間であった。
『死したお前を認め聞ける者の血肉によって蘇る』
あの言葉には続きがあったのだ。
『——それは、お前の心を奪った者だ』
だからお前に会いに行った。
レネ=オールストン。
お前が、僕の『蘇らせる者』だと知っていたんだ————。
そう心の中で呟きながらヴィリオは目の前の駒鳥を見つめる。
追い詰められながらも強い眼差しでこちらを見つめてくる女の唇をむさぼり組み敷いて自由を奪い、彼女が目を潤ませながらも屈辱に顔を歪めるその瞬間を想像すると……その日が待ちきれないヴィリオなのであった。
だからというわけではないが、レネ=オールストンは冬という季節が好きだった。
田舎では冬になれば雪が積もり、大人達は農作業もままならなくなるので家にこもって手仕事に精を出す。雪に覆われた外の世界は音がすべてあの白い平原に吸い込まれてしまったかのように静かで、天気の良い日に降り注ぐ光をきらきらと反射した。
都会に出てくると雪が降らないことに驚いたが、慣れてみるとこれはこれで悪くない。身を縮ませるような寒さの中歩いた後あたる暖炉の温もりは、幸福というものの象徴のようだ。大通りでは露店も数少なになっているが、外出している人はそう減っていない。彼らは早く暖炉にたどり着きたいというようにいそいそと歩き、暖かそうな灯りのともる家や酒場の中に吸い込まれていった。
いつもならそんな冬の雰囲気を楽しむところであるのだが、今のレネにはそうできない理由があった。
「……あのね、ついてこないでくれる?」
〈僕もこちらに用があるんだ〉
変態猥褻幽霊王がくっついて歩いてくるのだ。
しかも幽霊の状態で。
「あっそうじゃあ私あっちで別の用事済ませるから」
〈おっと偶然。僕もそちらでやることがあるんだった〉
しれっとした顔で幽霊王が方向転換したレネについてこようとしたその時、ぶちり、とレネの中で何かが切れた。
「あんた何か用事があるんじゃないわよねぇ! もーとっとと城に戻ってよ!」
〈残念ながらお前が一緒に城に戻って僕にキスしてくれないと誰も僕に気づかないから僕が寂しい〉
「知るか!」
レネとしては変態幽霊への正当な抗議であるのだが、いかんせん相手は幽霊。公共の場において、不利なのは彼女の方であった。
道ゆく人々が、虚空に向かって突然怒鳴り始めた彼女をざわざわと不審げな眼差しで見やる。それに気づいたレネ=オールストンは顔を真っ赤にして今度こそ幽霊王を無視すべくずんずんと歩き出したのだった。そして目当ての菓子店につくと乱暴に扉を開ける。
今日のオッリ=ベッカ座で行われる演目は、異国の『クリスマス』という祭りを題材にした『クリスマスの落し物』である。子供向けの作品なので子連れ客が多いのだが、例年子供客に配っていたお菓子を今年は用意し忘れたということで急遽レネが買い出しに出されたのである。
そこへ幽霊王が現れ、〈やぁレネ。僕と夜の散歩でもしないか?〉と言った時は気が遠くなった。
しかし彼女はどうにか、隣でじいとこちらを見つめてくる幽霊王を鋼鉄の意志で無視して必要な量の菓子を購入することに成功した。観客の子供に配る菓子の量はかなりのもので、店で借りた籠がいっぱいになったのでレネは誰かについてきてもらわなかったことを早々に後悔した。だが後の祭りである。大量の菓子を前にして立っているのはレネと使えない幽霊だけで、彼女は仕方なく一抱えもある籠を持って店を後にしたのだった。
〈大変そうだな。手伝いたいのは山々なのだが誰かさんがキスしてくれないから残念ながら僕は無力だ〉
〈こう寒いと人肌が恋しくなってくるな、そうだろう? 僕の寝台の隣はいつでもお前のためにあけてあるぞ〉
〈そういえば今夜の演目には出ないのか? またお前の珍妙な演技が見たいのに〉
などなど隣で世迷言を吐かれ続けてもレネはなんとか無視し続けたのだが、最後の台詞は無視できなかった。
〈去年のお前の『駒鳥の歌』での演技は見事だった〉
「見たの?」
思わず小声で問いかける。
するとヴィリオはにっこりと嬉しそうに笑ってから答えた。
〈ああ、台詞もない端役だったが、お前を見ていると空を飛んでいる駒鳥が本当に見えるようだった〉
それは褒め言葉のようにも聞こえたが、レネは眉を寄せた。
「嫌味なの?」
レネは、去年の『駒鳥の歌』では舞台上から落ちたのだ。空を飛ぶ駒鳥を目で追いかけるというだけの役だったのに、駒鳥を追いかけてふらふらと歩き出して舞台から落ちてしまった。幸い怪我はなかったものの、あの時も劇団長からこっぴどく叱られたものだ。
『駒鳥の歌』はレネにとって特別な演目だった。幼い頃、妖精の女王として舞台に立った。つまり初めて演じるということをした演目である。しかし今の彼女に大舞台で妖精の女王を演じる力量がないのは明らかで、去年は台詞のない一精霊の役に徹したのだった。
「王様が来てるなんて話聞かなかったけど」
〈お忍びだったからな。僕のことを敵対視してる人間が多すぎてうんざりしてたんだ。子供用の演目をやってる劇場なら見つかることもないだろうと思って逃げ込んだ〉
レネはぴたりと足を止めると、じっと幽霊王を見た。遠くでガラガラと馬車の走る音が聞こえる。
「もしかして、そこで私を見初めたとか?」
ヴィリオは以前からレネを知っているかのような口ぶりだった。けれどレネは会った覚えがない。舞台上での出会いならそれも理解できると思ったのだが、言ってすぐ馬鹿なことを口にしたと思った。
舞台から転げ落ちる間抜けな女優を見初める男がどこにいるというのだろう。
しかし王は笑って答えた。
〈そうかもな。お前という人間が気になり始めたのはそれが最初だ〉
騒がしかった馬車の音が近づいてきて、一度レネの横を通り過ぎたかと思うと急に停まった。そして中から見知った男性が飛び出してくる。
「オールストン嬢! そこにあの馬鹿はいないか!」
王の従者であるライナス=エレイン卿が『あの馬鹿』呼ばわりする相手はレネに知る限りただ一人である。
〈ライナスの奴、減俸だぞ〉
とヴィリオレイ王は苦々しく呟いたのだった。
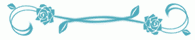
結局、レネは馬車に乗せられて王城に向かうことになった。
もちろん、死にかけている国王を救うためである。一度劇団に寄って菓子の籠を置いてきたが、ライナスが金のようなものを握らせると劇団長は嬉しそうに笑ってレネを見送った。
今現在、馬車の中はレネだけである。いや、正確にはレネと幽霊王がいた。
王を生き返らせる力を持つ《蘇らせる者》を捕獲したライナスは、突然王が死にかけてしまったことでやらなければならないことがたくさんあるあらしく、一足先に王城に戻っていってしまった。
〈ああせっかく密室で二人きりなのにお前に触れられないのが残念だ〉
「ねぇ、さっきの話だけど」
レネはヴィリオの口にした寝言をきっぱりと無視した。
「私を最初に認識したのが、前の冬よね? あんたが最初に死んだのはその冬の終わりでしょ? どうしてそんな短期間で、私があんたの《蘇らせる者》だってわかったの?」
『お前が僕を《蘇らせる者》だと知っていた』
そう言ったのはヴィリオ自身だ。レネにはずっと、あの台詞がひっかかっていた。自分とこの男にはどんな因縁があるというのだろう。
〈なんだ、そんなことを気にしていたのか〉
しかしヴィリオは破顔した。
「そりゃ気になるわよ。どういうわけなの? 教えなさいよ」
〈断る〉
笑顔のまま言下にそう言われ、レネは憤慨した。
「ちょっと」
しかし彼女の怒りはすぐにしぼんだ。ヴィリオが一呼吸の間に距離を詰め、レネを身動きできなくさせたからだ。
幽霊の彼には馬車の揺れでバランスを崩すことなどないらしい。ヴィリオはレネの正面に立ち、右膝を椅子に座る彼女の腿のすぐ横に置いて、左手はレネのすぐ後ろの壁に置いた。
相手が自分には触われないのだとわかってはいても、男性慣れしていないレネには危険信号が出る距離である。
肉体があったなら触れてしまいそうな距離でヴィリオが言った。
〈僕のことで悩むお前を見るのはたまらないよ。レネ=オールストン〉
(しまった。密室では、幽霊の方が有利だわ)
その時レネは大人しく馬車に乗ってしまったことを心から後悔したのだった。
触れられない幽霊相手では、突き飛ばして距離を取れないだけに狭い場所ではこちらの方が分が悪い。
赤くなった顔を今さら誤魔化すことはできないにしても、勝ったと思われたくないレネにはただ王を睨みつけることしかできないのだった。
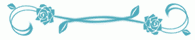
(まったく、これで無自覚なのだからタチが悪いな)
顔を赤くしたまま目を釣り上げられても、こちらとしては可愛いという感想しか出てこない。もし肉体があったならこのまま押し倒して屈服させて既成事実を作りたいところだが残念ながら彼はまだ幽霊なのであった。
ヴィリオレイ=レド=ネストルは心の中でため息をついた。
(ああ本当に、僕がこんな娘のためにいろいろと策略を巡らすはめになるとはね)
レネに言ったことは真実だ。
ヴィリオが彼女を認識したのは、去年の『駒鳥の歌』という演目が初めてであった。
見えない駒鳥を目だけで追う彼女の演技に驚いたのも確かだし、その後レネが舞台から落ちたことでその女優の顔は決定的にヴィリオの頭の中に記憶されることとなった。
城に戻って調べてみると、レネ=オールストンは売れない女優だった。
それからヴィリオはレネが出演する演目はなるべく見るようにしたが、どうにもその自分の情熱の理由を測りかねていた。
その理由というのが決定的になったのは、ヴィリオが暗殺されるひと月ほど前のことである。
彼はたまたま城を訪れていた宝石商から駒鳥のラペルピンを買った。それを目にして最初に思い浮かべたのがレネだったし、ヴィリオはレネの支援者になってもいいと思い始めていたので手始めにとそれをレネ=オールストン宛に贈ったのだ。
けれど、レネから礼の手紙が送られてくることはなかった。
ライナスの名を語ったので、相手が王だからと気後れしたわけではないはずだ。なら彼女は自分からの贈り物を無視したのかと思うと……ぞくぞくした。
ヴィリオレイ=レド=ネストルの嗜虐心に炎がついた瞬間であった。
『死したお前を認め聞ける者の血肉によって蘇る』
あの言葉には続きがあったのだ。
『——それは、お前の心を奪った者だ』
だからお前に会いに行った。
レネ=オールストン。
お前が、僕の『蘇らせる者』だと知っていたんだ————。
そう心の中で呟きながらヴィリオは目の前の駒鳥を見つめる。
追い詰められながらも強い眼差しでこちらを見つめてくる女の唇をむさぼり組み敷いて自由を奪い、彼女が目を潤ませながらも屈辱に顔を歪めるその瞬間を想像すると……その日が待ちきれないヴィリオなのであった。