28.辞書で頭を強打する
Open Menu
わたしは奮然と三年生の教室が並ぶ廊下を歩いていた。目当ての教室の前に来ると、開け放たれた扉の近くにいた女生徒に話しかける。
「すみません、安西先輩はいらっしゃいますか?」
「理子のこと?」
そう答えたのはすらっとした美人だ。
一緒にいたのは短い髪が爽やかな男子生徒。彼氏だろうか。どうでもいいけど。
「ちょっと待ってね。理子! お客さんよ」
まだ始業には時間があるせいか、教室の中に生徒は少ない。
「はいはーい、ちょっと待って。二十二、二十三、とこれでよし。全部あるわね。なに?」
教卓の上で何やら紙束を数えていた様子の生徒会長は、トントンとその束を揃えるとわたしと美人とその彼氏らしき男がいる後ろ側の出入り口に目を向けた。そして目を丸くする。
「あら? 八木原さんじゃない」
「あ、そっちに行きます」
教卓には前の出入り口の方が近い。わたしは美人に「ありがとうございました」と礼を言うと、足早に廊下を回って教室の前方の扉へ向かった。ちょうど廊下に出ようとしていた生徒会長とぶつかりそうになって謝る。
「あ、すみません」
「いえ、いいのよ。それよりどうしたの? 何か問題でも起きた?」
今日も相変わらずきちっと三つ編みをした生徒会長は、にっこりと優しく聞いた。わたしは登校鞄から紙を一枚取り出すと、それを生徒会長に押し付けた。まだ自分の教室にも行っていない。この用件を早く片付けてしまいたかったからだ。
「なに? これ……あらら」
A4の白い紙には、大きく退部届と書いてある。
昨日返してもらった生徒手帳を参照したところによると(もちろんスリーサイズなんかどこにも書いてなかった。あのクソエロ熊め)、退部届に特に書式はないらしく、名前と印鑑さえ押してあればいいらしい。
「受理してください」
「どうしたの? 突然。何かあったの?」
「何もありません。ただやめたいんです」
わたしは感情のないロボットのように答えた。
「うーん。一応、少し話しを聞きたいんだけど……昼休みにでも落ち着いて話さない?」
「受理してもらえないんですか?」
「そうじゃなくてね、あの……」
「それなら先生に提出するからいいです。すみませんが返してください」
「申し訳ないけどそれはできないわ。これは私が預かりました。一度保留よ。昼休みにもう一回話しましょう。それでいいわね?」
生徒会長はにっこり笑って言った。
有無を言わさぬその口調と圧力ある笑顔に、わたしは二の句を継げなくなる。
「……わかりました」
「よろしい。じゃあ今は教室に戻りなさい。昼休みに生徒会室でね」
「……はい」
ううう。
なんかよくわかんないけど生徒会長の笑顔はメンチ切ってる孝重郎より怖いんですけど。わたしはやって来た時の勢いを失って、とぼとぼと三年の廊下を逆戻りすることになってしまった。
くそー。
すぐにでもあんなフザけた部活退部してすっきりしたかったのに!
結局今朝は、ものすごく早起きしてものすごく早く家を出た。お迎えとやらと登校するのはまっぴらごめんだったからだ。公園で少し時間を潰し、時間になると学校へ向かってまっすぐこの三年の教室にやってきたのだ。
わたしはマド部を退部することに決めていた。
麗にはきちんと話して理解してもらおう。もしこれで友情が壊れたら……ということは考えない! 誠心誠意話したらわかってくれるはず!
そしてあのエロ熊にはもう二度と関わらない。
会わないし、目も合わせない。
それが最善なのだ。
もっとも望ましいこと。
心臓の奥に隠したものにはもう二度と触れることはない。
その蓋は開かない。
「おい、樋口!」
わたしは反射的に顔を上げた。
無意識に声の出所を探して見つける。三年A組の教室だ。開いたままの戸口から中が見える。
舜。
男子生徒に何かを手渡されて笑っている。
親しげに小突き合い、屈託なく喋っている。
なぜかわたしはひどく衝撃を受けた。
『兄貴の代わりを見つけたのか?』
先週の舜の言葉が蘇る。
彼はわたしを憎んでる。
憎んでいるのだ。
だからわたしの前でだけ笑わない。わたしの前でだけ吐き捨てるような台詞を口にして、わたしの前でだけ、あんな傷ついたような目をする。
当然だ。
舜の家庭を壊したのはわたしだった。
母は陰湿さを見せ、父は家に帰らなくなり、兄は出て行った。
わたしのせいだ。
わたしが奪った。
でも。
でもわたしはずっと、舜に許してほしかった。
彼にどんな罵声を浴びせかけられても、どんな憎悪の視線を投げつけられても、舜に許してほしかった。昔みたいに笑ってほしかった。
そして認めてほしかったのだ。わたしという人間を。
たった一人の兄妹だから。
「佐藤! 辞書返せよ」
「あーそうだったそうだった。投げるぞー」
「おい、危ねぇ!」
その警告の声に振り向く前に、わたしは側頭部に衝撃を受けて思考を乱した。
鈍器で殴りつけられたような衝撃だったが、後で聞いたかぎりそれは和英辞書だったらしい。
薄れゆく意識とひび割れた視界の中で、わたしは舜を見た気がした。
舜はこちらを見ると青ざめて駆け出す。円! と呼んだかもしれない。
妄想だろう。
ありえない。
舜はわたしの心配なんかしない。
わたしは笑った。
この心臓の奥にあるものは、これまでのわたしを裏切るものになるだろう。これが知れれば舜がわたしを許すこともきっとない。
だから隠す。
深く深く。
底に沈めて。
もう二度と触れない。
「……」
とりあえず。
佐藤め。覚えてろよ。
とわたしは最後に悪態をついて昏倒したのだった。
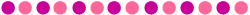
わたしは夢を見ていた。
昔の夢だ。
確か両親が法事か何かででかけていた夜、孝重郎と舜の三人でゲームをしたりお喋りをしたりした。
『あー! 負けたぁ!』
『俺に勝つなんて百年早い』
『円、次俺と代われよ!』
『えー、やだよ。舜もさっき二レースやったじゃん!』
『おい、喧嘩するなよ。舜。俺が代わってやるから』
『俺は兄貴と対戦したいんだよ。円弱ぇんだもん』
『なんですってぇ? いいわよ舜。受けてたとうじゃないの。あんたなんかぎったんぎったんのメッタンメッタンにしてやるんだから!』
『へぇー? 円サンが? 俺を?』
『きー! 孝重郎! 舜と代わって!』
『はいはい』
孝重郎が仕方なさそうな顔でコントローラーを舜に渡す。わたしと舜は睨み合ってテレビ画面に向き合った。
覚えてる。
この後結局わたしは負けて、舜の食器洗い当番を手伝わされたのだ。お互いに肘で小突き合って、笑いながら食器を洗った。孝重郎はそんなわたし達を呆れたように、けれど微笑ましそうに見ていた。
そう。
たぶんこれが、わたしの記憶の中で一番楽しかった思い出だ。
この後しばらくして、ノイローゼ気味になった樋口の母親のわたしに対する風当たりがいっそう強くなり、孝重郎はわたしを連れて家を出た。
それはきっとわたしを護るためだけではなく、家族を護るためでもあった。
彼はわたしをあのまま家に置いておくことが、母親に悪影響を及ぼすとわかっていたのだ。
わたしは異分子だった。
孝重郎はそんなわたしを一人にしないために、共に家を出てくれた。
わかってる。
それでもわたしはあの時、大丈夫だと言うべきだったのだ。
一人で大丈夫だと言うべきだった。
彼の優しさにつけこんだ。
そして永遠に失ってしまった。
昨日流した涙が、また頬を伝う。
楽しかった記憶はもう戻ってこない。そのことがひどく胸の奥を締め付けた。
誰かが「円」、と名前を呼んでその涙を拭ってくれる。
「……孝重郎」
その懐かしい声と指の温もりに呼吸が苦しくなり、わたしは喘ぐように彼の名を呼んだ。
「すみません、安西先輩はいらっしゃいますか?」
「理子のこと?」
そう答えたのはすらっとした美人だ。
一緒にいたのは短い髪が爽やかな男子生徒。彼氏だろうか。どうでもいいけど。
「ちょっと待ってね。理子! お客さんよ」
まだ始業には時間があるせいか、教室の中に生徒は少ない。
「はいはーい、ちょっと待って。二十二、二十三、とこれでよし。全部あるわね。なに?」
教卓の上で何やら紙束を数えていた様子の生徒会長は、トントンとその束を揃えるとわたしと美人とその彼氏らしき男がいる後ろ側の出入り口に目を向けた。そして目を丸くする。
「あら? 八木原さんじゃない」
「あ、そっちに行きます」
教卓には前の出入り口の方が近い。わたしは美人に「ありがとうございました」と礼を言うと、足早に廊下を回って教室の前方の扉へ向かった。ちょうど廊下に出ようとしていた生徒会長とぶつかりそうになって謝る。
「あ、すみません」
「いえ、いいのよ。それよりどうしたの? 何か問題でも起きた?」
今日も相変わらずきちっと三つ編みをした生徒会長は、にっこりと優しく聞いた。わたしは登校鞄から紙を一枚取り出すと、それを生徒会長に押し付けた。まだ自分の教室にも行っていない。この用件を早く片付けてしまいたかったからだ。
「なに? これ……あらら」
A4の白い紙には、大きく退部届と書いてある。
昨日返してもらった生徒手帳を参照したところによると(もちろんスリーサイズなんかどこにも書いてなかった。あのクソエロ熊め)、退部届に特に書式はないらしく、名前と印鑑さえ押してあればいいらしい。
「受理してください」
「どうしたの? 突然。何かあったの?」
「何もありません。ただやめたいんです」
わたしは感情のないロボットのように答えた。
「うーん。一応、少し話しを聞きたいんだけど……昼休みにでも落ち着いて話さない?」
「受理してもらえないんですか?」
「そうじゃなくてね、あの……」
「それなら先生に提出するからいいです。すみませんが返してください」
「申し訳ないけどそれはできないわ。これは私が預かりました。一度保留よ。昼休みにもう一回話しましょう。それでいいわね?」
生徒会長はにっこり笑って言った。
有無を言わさぬその口調と圧力ある笑顔に、わたしは二の句を継げなくなる。
「……わかりました」
「よろしい。じゃあ今は教室に戻りなさい。昼休みに生徒会室でね」
「……はい」
ううう。
なんかよくわかんないけど生徒会長の笑顔はメンチ切ってる孝重郎より怖いんですけど。わたしはやって来た時の勢いを失って、とぼとぼと三年の廊下を逆戻りすることになってしまった。
くそー。
すぐにでもあんなフザけた部活退部してすっきりしたかったのに!
結局今朝は、ものすごく早起きしてものすごく早く家を出た。お迎えとやらと登校するのはまっぴらごめんだったからだ。公園で少し時間を潰し、時間になると学校へ向かってまっすぐこの三年の教室にやってきたのだ。
わたしはマド部を退部することに決めていた。
麗にはきちんと話して理解してもらおう。もしこれで友情が壊れたら……ということは考えない! 誠心誠意話したらわかってくれるはず!
そしてあのエロ熊にはもう二度と関わらない。
会わないし、目も合わせない。
それが最善なのだ。
もっとも望ましいこと。
心臓の奥に隠したものにはもう二度と触れることはない。
その蓋は開かない。
「おい、樋口!」
わたしは反射的に顔を上げた。
無意識に声の出所を探して見つける。三年A組の教室だ。開いたままの戸口から中が見える。
舜。
男子生徒に何かを手渡されて笑っている。
親しげに小突き合い、屈託なく喋っている。
なぜかわたしはひどく衝撃を受けた。
『兄貴の代わりを見つけたのか?』
先週の舜の言葉が蘇る。
彼はわたしを憎んでる。
憎んでいるのだ。
だからわたしの前でだけ笑わない。わたしの前でだけ吐き捨てるような台詞を口にして、わたしの前でだけ、あんな傷ついたような目をする。
当然だ。
舜の家庭を壊したのはわたしだった。
母は陰湿さを見せ、父は家に帰らなくなり、兄は出て行った。
わたしのせいだ。
わたしが奪った。
でも。
でもわたしはずっと、舜に許してほしかった。
彼にどんな罵声を浴びせかけられても、どんな憎悪の視線を投げつけられても、舜に許してほしかった。昔みたいに笑ってほしかった。
そして認めてほしかったのだ。わたしという人間を。
たった一人の兄妹だから。
「佐藤! 辞書返せよ」
「あーそうだったそうだった。投げるぞー」
「おい、危ねぇ!」
その警告の声に振り向く前に、わたしは側頭部に衝撃を受けて思考を乱した。
鈍器で殴りつけられたような衝撃だったが、後で聞いたかぎりそれは和英辞書だったらしい。
薄れゆく意識とひび割れた視界の中で、わたしは舜を見た気がした。
舜はこちらを見ると青ざめて駆け出す。円! と呼んだかもしれない。
妄想だろう。
ありえない。
舜はわたしの心配なんかしない。
わたしは笑った。
この心臓の奥にあるものは、これまでのわたしを裏切るものになるだろう。これが知れれば舜がわたしを許すこともきっとない。
だから隠す。
深く深く。
底に沈めて。
もう二度と触れない。
「……」
とりあえず。
佐藤め。覚えてろよ。
とわたしは最後に悪態をついて昏倒したのだった。
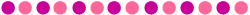
わたしは夢を見ていた。
昔の夢だ。
確か両親が法事か何かででかけていた夜、孝重郎と舜の三人でゲームをしたりお喋りをしたりした。
『あー! 負けたぁ!』
『俺に勝つなんて百年早い』
『円、次俺と代われよ!』
『えー、やだよ。舜もさっき二レースやったじゃん!』
『おい、喧嘩するなよ。舜。俺が代わってやるから』
『俺は兄貴と対戦したいんだよ。円弱ぇんだもん』
『なんですってぇ? いいわよ舜。受けてたとうじゃないの。あんたなんかぎったんぎったんのメッタンメッタンにしてやるんだから!』
『へぇー? 円サンが? 俺を?』
『きー! 孝重郎! 舜と代わって!』
『はいはい』
孝重郎が仕方なさそうな顔でコントローラーを舜に渡す。わたしと舜は睨み合ってテレビ画面に向き合った。
覚えてる。
この後結局わたしは負けて、舜の食器洗い当番を手伝わされたのだ。お互いに肘で小突き合って、笑いながら食器を洗った。孝重郎はそんなわたし達を呆れたように、けれど微笑ましそうに見ていた。
そう。
たぶんこれが、わたしの記憶の中で一番楽しかった思い出だ。
この後しばらくして、ノイローゼ気味になった樋口の母親のわたしに対する風当たりがいっそう強くなり、孝重郎はわたしを連れて家を出た。
それはきっとわたしを護るためだけではなく、家族を護るためでもあった。
彼はわたしをあのまま家に置いておくことが、母親に悪影響を及ぼすとわかっていたのだ。
わたしは異分子だった。
孝重郎はそんなわたしを一人にしないために、共に家を出てくれた。
わかってる。
それでもわたしはあの時、大丈夫だと言うべきだったのだ。
一人で大丈夫だと言うべきだった。
彼の優しさにつけこんだ。
そして永遠に失ってしまった。
昨日流した涙が、また頬を伝う。
楽しかった記憶はもう戻ってこない。そのことがひどく胸の奥を締め付けた。
誰かが「円」、と名前を呼んでその涙を拭ってくれる。
「……孝重郎」
その懐かしい声と指の温もりに呼吸が苦しくなり、わたしは喘ぐように彼の名を呼んだ。