20.ご近所迷惑になる
Open Menu
やっと土曜日である。うちの学校ではなぜか始業式後の最初の土曜日は休みと決まっていて、今日明日と連休となる。やったー!
朝ご飯はバターをのせてパンを焼いて、目玉焼きを作ってほうれん草と卵を炒めたのですませた。天気がいいので洗濯機を回している間に軽く掃除。
ふー。
こういう休日って本当に清々しいね!
このアパートは数年前にウメが当時付き合ってた金持ちに買ってもらったもので、八十歳の平野トメ乃さんを管理人として雇って一階に住んでもらっている。樋口の家を出ることになったわたしがトメ乃さんに相談すると、彼女は快く空いている部屋に住むといいと言ってくれた。ちなみに間取りは1K。キッチンは普通の部屋くらいの広さあるし一人暮らしには十分な部屋だ。
『大丈夫、家賃ならウメさんからもらいますよ。円ちゃんは未成年ですからね。気にすることないですよ』
そう言ったトメ乃さんをわたしがどんなに心強く思ったことか。
ちなみにわたしはウメと直接連絡を取れる状況にはない。まぁトメ乃さんにとってウメは雇用主なんだから連絡は取れるんだろうけど、特に会いたいとも思わないし。そういうわけでかれこれ三年? くらいウメには会っていない。
もちろんあの馬鹿女のことだからゴキブリのようにしぶとくどこかで生きているんだと思うけど。
ともかくそんなわが家でとりあえずの家事を終えて一息ついたわたしは、カーペットの上のクッションに座ってホットミルクを飲みながらバイト情報誌を読むことにした。
とりあえず部活には入ったけれどあのフザけた部活に毎日の活動があるとは思えないし、好きにバイトも入れていいだろう。
うーん。本屋さんとかいいなぁ。でもやっぱり飲食系かな。まかないとかで食費も浮くだろうし。
あーでもないこーでもないと唸っているうちに洗濯機が止まったので洗濯物を干す。そうしながら、今日の昼はなんの鶏肉料理にしようかなぁ、と思案する。なにせ今うちには大量の鶏肉が冷凍されていらっしゃるのだ!
親子丼とかいいかも。卵あったよね。昼食のメニューを考えながら洗濯物を干していると、下の方から人が喧嘩するような声が聞こえた。
「私達がここに立っていて何かあなたにご迷惑をおかけしましたか?」
「いや、ですからね、あなたのような人が往来で立っていると住民が怯えるんですよ」
「ではその住民とやらを全員ここへ呼んでいただけますか? 私達が無害だということを教えてさしあげますから」
なんだなんだと思って上から覗き込んでみると、どうやらこのアパートの前でモメているのは三人の男のようである。
あの小太りの背中は……一階に住む自称作家の内田さんじゃないだろうか。あー。あの人締め切りが近くなると相手構わず当たり散らすんだよね。右手に近くの弁当屋のビニール袋を下げているところを見るとお昼でも買ってきたのかな?
そしてなんと彼が怒鳴りつけているのはどこからどう見てもヤクザだ。
後ろになでつけられた髪、派手なシャツと、高級そうなスーツ。ひえええ。内田さん、もっと相手選んだ方がいいよ! と思ったが、そのヤクザの隣にいる男はどうもヤクザらしくない。今流行の漫画に出てくる犬(?)のキャラクターが印刷されたTシャツとジーンズを履いている。髪はちゃらちゃらした茶髪。斜め掛けの鞄を持っているその雰囲気は学生っぽい。
……。いや、なんかあのヤクザとTシャツってすごく見覚えあるな。
わたしは慌てて部屋を飛び出すと、カンカンと音を立てて階段を降り、なおもモメている三人のもとへ走った。
「大体あんたらみたいな奴らがいるから世の中よくならねぇんだよ!」
「なるほど。根拠薄弱な非難にはこちらも相応の対応をさせていただきますよ」
ちょ、待て!
「まー君!」
わたしは叫んだ。
すると男三人が同時にこちらを振り向く。内田さんは怪訝そうな顔をして、Tシャツはぱっと顔を輝かせた。そしてヤクザがにやりと口の端を上げて笑う。
「よお、円」
「何やってんのよ! まー君もみさをちゃんも!」
「円ぁー会いたかったぜー」
Tシャツが両手を広げて抱きついてきた。
「お前がちゃんと生活してるのかと思ってよ、外から見てたんだけどそしたらこの兄さんがいちゃもんつけてきてな?」
ヤクザが肩をすくめると、内田さんがわたしをぎろりと睨む。
「あんたの知り合いか?」
たぶんわたしが同じアパートの住人だってことはわかるけど名前まではわからないのだろう。
「すいません! 知り合いなんです。よく言ってきかせますんで」
そう言って頭を下げると、内田さんはちっと舌打ちをして「頼むよ、ほんと」と捨て台詞を履いて一〇四号室の自分の部屋に戻っていった。
「あいつボコっとく?」
まだわたしに抱きついたままのみさをちゃんがにこにこと子犬のような笑顔で言う。
「駄目!」
こいつほんとにしかねん! と思ってわたしは慌ててそれを止めた。
「まー君とか本業でしょ! 一般人に何やってんのよ!」
まー君こと姫川誠は、見た目通りのヤクザだ。下っ端だけど。そして結城みさをは大学五回生。学年は三年。嘆かわしい。
「俺は何もしてねぇよ」
まー君が心外そうに眉を上げる。
「いたって紳士的に対応してただろ? なぁみさを」
「ああ。昔の誠なら今頃はここに肉団子が転がってたんじゃないの?」
あははー。とみさをちゃんが笑う。
笑いごとじゃないんだけどね!
「キヨ君は?」
「清雨は仕事。あいつもー完全にサラリーマンだぜ?」
「そうそう、円聞いてよ! 清雨好きな子できたんだよ。なのに俺達には紹介してくれねーの。ひどくない?」
普通『好きな人』という段階で友達に紹介したりはしないだろう。
「と、ともかく! うち上がってよ。ここは平和な住宅街なんだよ。二人でいるとすごい目立つよ」
「おう。それなら円、出かける支度してこいよ」
まー君が言った。
「昼飯奢ってやる」
ら、ラッキー! 親子丼がステーキ定食に早変わりだぜ!
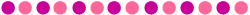
姫川誠と結城みさをと加藤清雨は孝重郎の友達だった。
『歩く殺戮ロボ』と呼ばれていた孝重郎だけど、彼が本当にロボットというわけなのではなく、ただの不器用で優しい男なのだということを知っている友人がいたのは、わたしにとって嬉しいことだった。
特にまー君こと姫川誠は当時『殺戮姫』呼ばれて孝重郎と喧嘩しまくっていた。調子のいいみさをちゃんと、真面目なキヨ君と四人で、彼らはとても仲が良さそうだった。
ある日わたしは、彼ら四人が数人の他校生と空き地で喧嘩しているところを偶然見かけてしまった。
その中の一人が孝重郎だと気付いたわたしは、なぜかそこを動くことができずにじっと孝重郎の飛び散る唾や血を見て、鈍い殴打の音とうめき声を聞いていた。
四人はぼろぼろになりながらも勝利した。
そして相手の心など何もかもわかっているかのような笑みを交わして、みさをちゃんが取り出した一本の煙草を四人で吸った。
わたしはまるで映画のワンシーンを見ているような気持ちになった。最初にわたしに気付いたのはキヨ君で、孝重郎は呆然とそこに突っ立っているのが数日前に彼の家にやってきた義理の妹だと気付いて目を丸くした。
彼が優しい人だと気付くのに時間は必要なかった。
だって彼は短く息を吐くと、わたしを一瞥してから空き地を出て行った。わたしがどうしたらいいかわからずにまだそこに立っていると、それに気付いて立ち止まり、仕方がなさそうな顔で振り向いてずっと待っていてくれた。
わたしが歩き出すのを。
その一歩を踏み出すのを。
彼はずっと待っていてくれたのだ。
樋口孝重郎は、そういう男だった。
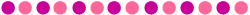
「牛肉うま!」
わたしはステーキ肉を頬張って幸せいっぱいな気持ちになった。
場所は駅の近くの定食屋さん。ずっと前から気になってたんだよね!
はー。牛肉さんってほんとすごいわー。
みさをちゃんはハンバーグ定食で、まー君は和定食。正直わたし達はちょっと周囲の視線を集めている。だって明らかに変な取り合わせだし。ヤクザと茶髪大学生と黒髪眼鏡女子ってどんなよ。
でもそんなことは気にしない! 今が栄養を取るチャンス! とばかりにわたしはステーキにがっついた。
「なぁなぁ円ぁ、今度俺に制服着て見せてよ」
「は? なんで?」
「女子高生だぜ? たまらん。あ、後で下着買ってやるからそれ下に着てさ」
みさをちゃんはちょっとオタクな変態なのである。それなりにかっこいいと思うのに残念!
「これから夏だろー。制服から透けてみえるブラジャーがなんとも言えず下半身にくるよなー。しかも俺が買ってやったやつ着けてるのかと思うとなおさら……くふふ」
「みさをちゃんなんか変態に磨きがかかってるね」
「恋人は二次元だぜ!」
「きっつ!」
食事をしながらもぺちゃくちゃと喋るわたし達とは違い、まー君はお箸を使って上品に食べている。ヤクザのくせに。
やがて食事を終えたわたし達は、コーヒーを飲んで一息ついた。
「ぷはー。お腹いっぱい。大満足! ありがとうまー君!」
「どういたしまして」
「俺にもお礼言って? 円。できれば上目遣いで胸元見せて」
「お前は金払ってねぇだろ、みさを」
「だってー。円に『ありがとう』って言われたい。できれば『お願い』も言われたい。上目遣いで」
「キヨ君は元気?」
なんだかみさをちゃんは軽く暴走気味なので無視することにしてわたしは聞いた。
「ああ。あいつも円のこと気にしてたよ」
「そっかー」
「今度四人でご飯食べるか?」
「え、ほんと? 食べる食べる」
わたしが笑って言うと、まー君がふっと優しく微笑んだ。
「お前、大分元気になったな」
「まーね、いつまでも落ち込んでても仕方がないし」
その節はお世話になりましたー、とわたしは照れるように頭を掻いた。
息をしながら死んでいるようだったわたしを彼らがずっと心配してくれていたのは知っていた。けれどなかなか立ち上がることはできなかった。世界は鈍く暗い色に染められて、どんな声もわたしに届いてくることはなかった。
「そういや円、あれから弟と喋ったの?」
みさをちゃんが聞く。
『弟』とは舜のことだ。
「うん。同じ学校だしね、少し話すよ」
「なんかされたら言えよ。俺が半殺しにしてやるから。あれくらいの年は抑え込むと爆発するからなー。爆発したら血の繋がりとかマジ関係ねぇから。いいか、円。襲われたらまずいきり立ってる急所を蹴り上げろよ」
まさか昨日頭突きかまされそうになりました、とは言えない。
みさをちゃんなら本当に半殺しにしかねない。
「まぁ弟もなー。かわいそうな奴だけどなー。欲しい女が他人のもんでしかもそれが自分の兄……」
とみさをちゃんがわけのわからない話を始めた時、ゴン! とすぐ横の窓が叩かれた。
びくりとしたわたしは窓の外を見て唖然と口を開ける。
や、やべ! 死んだふり!
とその場に突っ伏そうとしたがこいつ実は人間だからそんなの意味ないんだ! と気付いて頭をかきむしりたくなる。
どうしてここで現れる!?
しかしそんな心中の悲鳴が聞こえるはずもなくわたしを見てにやりと笑った奴は、当たり前のようにお店に入ってきて、わたしと同じテーブルに座るヤクザと茶髪大学生に物怖じする様子一つなく言った。
「偶然だな円。何やってんだ?」
「……」
「……」
まー君もみさをちゃんもガンつけないで!
私は再び心の中で叫んだ。
「……こいつは誰だ、円」
とまー君が厳しい顔で聞いてくる。
「く……部活の先輩です」
あやうく熊男と言いそうになったわたしは最も無難な答えをはじき出してそう答えたのだった。
朝ご飯はバターをのせてパンを焼いて、目玉焼きを作ってほうれん草と卵を炒めたのですませた。天気がいいので洗濯機を回している間に軽く掃除。
ふー。
こういう休日って本当に清々しいね!
このアパートは数年前にウメが当時付き合ってた金持ちに買ってもらったもので、八十歳の平野トメ乃さんを管理人として雇って一階に住んでもらっている。樋口の家を出ることになったわたしがトメ乃さんに相談すると、彼女は快く空いている部屋に住むといいと言ってくれた。ちなみに間取りは1K。キッチンは普通の部屋くらいの広さあるし一人暮らしには十分な部屋だ。
『大丈夫、家賃ならウメさんからもらいますよ。円ちゃんは未成年ですからね。気にすることないですよ』
そう言ったトメ乃さんをわたしがどんなに心強く思ったことか。
ちなみにわたしはウメと直接連絡を取れる状況にはない。まぁトメ乃さんにとってウメは雇用主なんだから連絡は取れるんだろうけど、特に会いたいとも思わないし。そういうわけでかれこれ三年? くらいウメには会っていない。
もちろんあの馬鹿女のことだからゴキブリのようにしぶとくどこかで生きているんだと思うけど。
ともかくそんなわが家でとりあえずの家事を終えて一息ついたわたしは、カーペットの上のクッションに座ってホットミルクを飲みながらバイト情報誌を読むことにした。
とりあえず部活には入ったけれどあのフザけた部活に毎日の活動があるとは思えないし、好きにバイトも入れていいだろう。
うーん。本屋さんとかいいなぁ。でもやっぱり飲食系かな。まかないとかで食費も浮くだろうし。
あーでもないこーでもないと唸っているうちに洗濯機が止まったので洗濯物を干す。そうしながら、今日の昼はなんの鶏肉料理にしようかなぁ、と思案する。なにせ今うちには大量の鶏肉が冷凍されていらっしゃるのだ!
親子丼とかいいかも。卵あったよね。昼食のメニューを考えながら洗濯物を干していると、下の方から人が喧嘩するような声が聞こえた。
「私達がここに立っていて何かあなたにご迷惑をおかけしましたか?」
「いや、ですからね、あなたのような人が往来で立っていると住民が怯えるんですよ」
「ではその住民とやらを全員ここへ呼んでいただけますか? 私達が無害だということを教えてさしあげますから」
なんだなんだと思って上から覗き込んでみると、どうやらこのアパートの前でモメているのは三人の男のようである。
あの小太りの背中は……一階に住む自称作家の内田さんじゃないだろうか。あー。あの人締め切りが近くなると相手構わず当たり散らすんだよね。右手に近くの弁当屋のビニール袋を下げているところを見るとお昼でも買ってきたのかな?
そしてなんと彼が怒鳴りつけているのはどこからどう見てもヤクザだ。
後ろになでつけられた髪、派手なシャツと、高級そうなスーツ。ひえええ。内田さん、もっと相手選んだ方がいいよ! と思ったが、そのヤクザの隣にいる男はどうもヤクザらしくない。今流行の漫画に出てくる犬(?)のキャラクターが印刷されたTシャツとジーンズを履いている。髪はちゃらちゃらした茶髪。斜め掛けの鞄を持っているその雰囲気は学生っぽい。
……。いや、なんかあのヤクザとTシャツってすごく見覚えあるな。
わたしは慌てて部屋を飛び出すと、カンカンと音を立てて階段を降り、なおもモメている三人のもとへ走った。
「大体あんたらみたいな奴らがいるから世の中よくならねぇんだよ!」
「なるほど。根拠薄弱な非難にはこちらも相応の対応をさせていただきますよ」
ちょ、待て!
「まー君!」
わたしは叫んだ。
すると男三人が同時にこちらを振り向く。内田さんは怪訝そうな顔をして、Tシャツはぱっと顔を輝かせた。そしてヤクザがにやりと口の端を上げて笑う。
「よお、円」
「何やってんのよ! まー君もみさをちゃんも!」
「円ぁー会いたかったぜー」
Tシャツが両手を広げて抱きついてきた。
「お前がちゃんと生活してるのかと思ってよ、外から見てたんだけどそしたらこの兄さんがいちゃもんつけてきてな?」
ヤクザが肩をすくめると、内田さんがわたしをぎろりと睨む。
「あんたの知り合いか?」
たぶんわたしが同じアパートの住人だってことはわかるけど名前まではわからないのだろう。
「すいません! 知り合いなんです。よく言ってきかせますんで」
そう言って頭を下げると、内田さんはちっと舌打ちをして「頼むよ、ほんと」と捨て台詞を履いて一〇四号室の自分の部屋に戻っていった。
「あいつボコっとく?」
まだわたしに抱きついたままのみさをちゃんがにこにこと子犬のような笑顔で言う。
「駄目!」
こいつほんとにしかねん! と思ってわたしは慌ててそれを止めた。
「まー君とか本業でしょ! 一般人に何やってんのよ!」
まー君こと姫川誠は、見た目通りのヤクザだ。下っ端だけど。そして結城みさをは大学五回生。学年は三年。嘆かわしい。
「俺は何もしてねぇよ」
まー君が心外そうに眉を上げる。
「いたって紳士的に対応してただろ? なぁみさを」
「ああ。昔の誠なら今頃はここに肉団子が転がってたんじゃないの?」
あははー。とみさをちゃんが笑う。
笑いごとじゃないんだけどね!
「キヨ君は?」
「清雨は仕事。あいつもー完全にサラリーマンだぜ?」
「そうそう、円聞いてよ! 清雨好きな子できたんだよ。なのに俺達には紹介してくれねーの。ひどくない?」
普通『好きな人』という段階で友達に紹介したりはしないだろう。
「と、ともかく! うち上がってよ。ここは平和な住宅街なんだよ。二人でいるとすごい目立つよ」
「おう。それなら円、出かける支度してこいよ」
まー君が言った。
「昼飯奢ってやる」
ら、ラッキー! 親子丼がステーキ定食に早変わりだぜ!
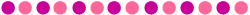
姫川誠と結城みさをと加藤清雨は孝重郎の友達だった。
『歩く殺戮ロボ』と呼ばれていた孝重郎だけど、彼が本当にロボットというわけなのではなく、ただの不器用で優しい男なのだということを知っている友人がいたのは、わたしにとって嬉しいことだった。
特にまー君こと姫川誠は当時『殺戮姫』呼ばれて孝重郎と喧嘩しまくっていた。調子のいいみさをちゃんと、真面目なキヨ君と四人で、彼らはとても仲が良さそうだった。
ある日わたしは、彼ら四人が数人の他校生と空き地で喧嘩しているところを偶然見かけてしまった。
その中の一人が孝重郎だと気付いたわたしは、なぜかそこを動くことができずにじっと孝重郎の飛び散る唾や血を見て、鈍い殴打の音とうめき声を聞いていた。
四人はぼろぼろになりながらも勝利した。
そして相手の心など何もかもわかっているかのような笑みを交わして、みさをちゃんが取り出した一本の煙草を四人で吸った。
わたしはまるで映画のワンシーンを見ているような気持ちになった。最初にわたしに気付いたのはキヨ君で、孝重郎は呆然とそこに突っ立っているのが数日前に彼の家にやってきた義理の妹だと気付いて目を丸くした。
彼が優しい人だと気付くのに時間は必要なかった。
だって彼は短く息を吐くと、わたしを一瞥してから空き地を出て行った。わたしがどうしたらいいかわからずにまだそこに立っていると、それに気付いて立ち止まり、仕方がなさそうな顔で振り向いてずっと待っていてくれた。
わたしが歩き出すのを。
その一歩を踏み出すのを。
彼はずっと待っていてくれたのだ。
樋口孝重郎は、そういう男だった。
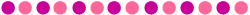
「牛肉うま!」
わたしはステーキ肉を頬張って幸せいっぱいな気持ちになった。
場所は駅の近くの定食屋さん。ずっと前から気になってたんだよね!
はー。牛肉さんってほんとすごいわー。
みさをちゃんはハンバーグ定食で、まー君は和定食。正直わたし達はちょっと周囲の視線を集めている。だって明らかに変な取り合わせだし。ヤクザと茶髪大学生と黒髪眼鏡女子ってどんなよ。
でもそんなことは気にしない! 今が栄養を取るチャンス! とばかりにわたしはステーキにがっついた。
「なぁなぁ円ぁ、今度俺に制服着て見せてよ」
「は? なんで?」
「女子高生だぜ? たまらん。あ、後で下着買ってやるからそれ下に着てさ」
みさをちゃんはちょっとオタクな変態なのである。それなりにかっこいいと思うのに残念!
「これから夏だろー。制服から透けてみえるブラジャーがなんとも言えず下半身にくるよなー。しかも俺が買ってやったやつ着けてるのかと思うとなおさら……くふふ」
「みさをちゃんなんか変態に磨きがかかってるね」
「恋人は二次元だぜ!」
「きっつ!」
食事をしながらもぺちゃくちゃと喋るわたし達とは違い、まー君はお箸を使って上品に食べている。ヤクザのくせに。
やがて食事を終えたわたし達は、コーヒーを飲んで一息ついた。
「ぷはー。お腹いっぱい。大満足! ありがとうまー君!」
「どういたしまして」
「俺にもお礼言って? 円。できれば上目遣いで胸元見せて」
「お前は金払ってねぇだろ、みさを」
「だってー。円に『ありがとう』って言われたい。できれば『お願い』も言われたい。上目遣いで」
「キヨ君は元気?」
なんだかみさをちゃんは軽く暴走気味なので無視することにしてわたしは聞いた。
「ああ。あいつも円のこと気にしてたよ」
「そっかー」
「今度四人でご飯食べるか?」
「え、ほんと? 食べる食べる」
わたしが笑って言うと、まー君がふっと優しく微笑んだ。
「お前、大分元気になったな」
「まーね、いつまでも落ち込んでても仕方がないし」
その節はお世話になりましたー、とわたしは照れるように頭を掻いた。
息をしながら死んでいるようだったわたしを彼らがずっと心配してくれていたのは知っていた。けれどなかなか立ち上がることはできなかった。世界は鈍く暗い色に染められて、どんな声もわたしに届いてくることはなかった。
「そういや円、あれから弟と喋ったの?」
みさをちゃんが聞く。
『弟』とは舜のことだ。
「うん。同じ学校だしね、少し話すよ」
「なんかされたら言えよ。俺が半殺しにしてやるから。あれくらいの年は抑え込むと爆発するからなー。爆発したら血の繋がりとかマジ関係ねぇから。いいか、円。襲われたらまずいきり立ってる急所を蹴り上げろよ」
まさか昨日頭突きかまされそうになりました、とは言えない。
みさをちゃんなら本当に半殺しにしかねない。
「まぁ弟もなー。かわいそうな奴だけどなー。欲しい女が他人のもんでしかもそれが自分の兄……」
とみさをちゃんがわけのわからない話を始めた時、ゴン! とすぐ横の窓が叩かれた。
びくりとしたわたしは窓の外を見て唖然と口を開ける。
や、やべ! 死んだふり!
とその場に突っ伏そうとしたがこいつ実は人間だからそんなの意味ないんだ! と気付いて頭をかきむしりたくなる。
どうしてここで現れる!?
しかしそんな心中の悲鳴が聞こえるはずもなくわたしを見てにやりと笑った奴は、当たり前のようにお店に入ってきて、わたしと同じテーブルに座るヤクザと茶髪大学生に物怖じする様子一つなく言った。
「偶然だな円。何やってんだ?」
「……」
「……」
まー君もみさをちゃんもガンつけないで!
私は再び心の中で叫んだ。
「……こいつは誰だ、円」
とまー君が厳しい顔で聞いてくる。
「く……部活の先輩です」
あやうく熊男と言いそうになったわたしは最も無難な答えをはじき出してそう答えたのだった。