27.奪われる
Open Menu
「ななななななんの用ですか?」
「まぁまぁいいからちょっと家にいれろや」
ヤ、ヤクザ! ヤクザのものいいだこれは! まー君たすけてー!
「嫌ですよ! 女子の一人暮らしですよここは。非常識な!」
「いいから入れろって」
「帰ってください!」
思い切りノブを引っ張って扉を閉めようとしたわたしは、けれどその扉がガツンと音を立てて何かに引っかかったので青ざめた。
なんと熊が脚をねじこんできている!
ぎゃー!
「ちょ、何してんですか!」
「いってえなぁお前」
「け、警察呼びますよ!」
「ほお? そんなこと言っていいのか?」
熊はポケットから何かを取り出すと、扉の隙間に持ってきてひらひらとさせた。
生徒手帳だ。
たぶん、わたしの。
あれに住所も書いてある。熊はそれを見ながらここへ来たんだろう。
「なくしたことにするんで別にいいです」
どうせ去年からずーっとポケットの中に入っててその存在すら忘れてたくらいなんだから。
「ほー。えーと、なになに? 八木原円、血液型A型、へぇお前九月生まれなのか。なになに? バスト八十……」
「ぎゃああああ!」
「うるせぇな。ご近所迷惑になるだろ」
「そんなこと生徒手帳に書いてあるわけないだろ!」
「は? お前知らねぇの? 入学した時に健康診断あっただろ? あの時に身体データは全部生徒手帳に書き込まれるんだぞ」
……そ、そうなのか!?
生徒手帳なんて一回も開いたことないから知らなかった……! そんな個人情報の詰まった機密書類だったなんて!
「か、返せ!」
「なら部屋に入れろ」
「なんでだよ!」
「いいからほら、もう観念しろって。な? 別になんもしねぇから」
「……」
わたしは熊を睨みつけた。
何もしないのならなぜ部屋に入る必要があるというのだ。くそ。この変態熊め! さっきの動悸はやっぱりただの神経伝達ミスだ。ああ、わたしの動揺も返せ!
「……すぐ帰ってくださいよ」
しぶしぶそう言うと、熊はにっこりと無邪気に笑ってようやく扉に挟んでいた脚を引いた。一度扉を閉めて、チェーンに手をかけながらしばし逡巡する。
よく考えろ。
本当に家に入れていいのか、あれ?
熊だよ熊。猛獣だよ。
ぐわっと噛み付かれただどうしよう。
そう思ったわたしはふと思いついて部屋の中に戻ると、隅に置いてある収納棚から小ぶりな機械を取り出した。スタンガンだ。昔孝重郎が護身用にと渡してくれた。
それをいそいそと制服のポケットに入れる。
うーん、ちょっとぽっこりしてるけどまぁばれないだろう。
よし、これで安心!
「おい、まだかよ」
扉の向こうから熊が急かす。
「今開けますよ!」
わたしは言ってチェーンを外した。そしてガチャリと再び扉を開ける。
するとにやにやと笑う熊が視界に入った。
「……さぁ、返してください」
熊の手はポケットに入れられていて、生徒手帳は見えない。制服姿のままではあるが、相変わらず手ぶらのようだ。
奴はつと差し出したわたしの手を無視して、ぐいとわたしを押しのけるとずかずかと部屋に入ってきた。
「へー、結構綺麗にしてんじゃねぇか」
「返せよ!」
「まぁ落ち着けって。お前、夕飯は? まぁその格好じゃまだ食べてねぇよな。こないだの鶏肉まだあんのか?」
「……ありますけど」
「じゃあ唐揚げにしてくれ」
「やだよ!」
なんでお前のために揚げ物なんて面倒臭いことをしなければならないんだ!
「仕方ねぇなぁ。親子丼でいいよ」
「一昨日食べた」
「俺は一昨日フォアグラのテリーヌだった」
し、ね!
この時わたしは本当に心からそう思った。格差社会は滅亡すればいいのに。
しかし熊はそんな怨念のこもった視線に気付くことなく、図々しくずかずかと畳の敷いてある部屋に入るとどかりとそこに腰を降ろした。
「なぁ、テーブルねぇの?」
「……そこに立てかけてあります」
「なぁ、なんで布団出てんの? しかもぐちゃぐちゃ」
「……」
わたしはなんだかどっと疲れてしまった。
かくなる上は一刻も早く熊には満足してもらってお帰りいただいた方がいいだろう。さいわい鶏肉も卵も玉ねぎもまだ冷蔵庫に入っている。
深くため息をついたわたしは、熊様ご所望のお供え物を作るため、冷蔵庫を開けた。
……ああ、せめて制服着替えたいんだけどな……。
けれど堂々と覗きそうな熊がいる場所で、着替える気にはならない八木原円であった。
トホホ。
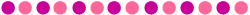
「はい、どうぞ」
「おー。うまそうじゃねぇか」
熊に孝重郎の箸を使わせる気は毛の先ほどもなかったので、わたしはたまたまあった割り箸を出した。(なかったら手で食えって言ってやったのに。ちっ)熊は割り箸を持って「いただきます」とお行儀よく言って、パシ、と小気味いい音を立てて箸を割るとわたしが作った親子丼をぱくぱく食べた。
「……」
熊の正面に座って自分の箸で親子丼を食べながら、わたしは少し驚いていた。
庶民が作った庶民的丼を左手に割り箸を右手に持っているというのに、熊の食事の所作はどことなく上品だ。てっきり体育会系男子のようにご飯を掻き込むんだと思ってたのに、一口一口きちんと味わっている感じがする。
思わすじーっと見入っていたわたしと目が合うと、熊はまたあの子供のような笑顔を見せた。
「うめぇじゃねぇか」
うぐ。
と喉に何かが詰まったような感覚がしたので、慌てて水を飲む。
「お前どれくらい一人暮らししてんの?」
「……一年です」
一人暮らしなら一年だ。
「ふうん。二人暮らしはどれくらいしてたんだ?」
そう問われてわたしはぎょっとした。
え? そんなことまで生徒手帳って書いてあるの?
すると熊はにやりと笑って答える。
「この部屋にゃお前の匂いが染み付いてる。一年だけ住んでたわけじゃねぇだろ? 三人以上住むには手狭だ。だから一年以上前は二人暮らしだった。違うか?」
「……」
なにこいつ怖いんだけど。匂い? なのそれ。本当に獣なの?
「……綾小路先輩には関係ないですよね?」
「ああないね。でも俺はお前に興味がある」
「迷惑です」
「まぁそう言うなって」
魔王の言葉が蘇る。
『玄は、純粋に新しいおもちゃとして、君を気に入っているんだ』
おもちゃ? 冗談じゃない。
わたしは誰かのおもちゃなんかになる気は一切ないんだ。
そう頭の中で悪態をつくと、意を決して切り出す。
「あのですね、綾小路先輩。本当に全部迷惑なんです。マド部とかいう活動もやめてください。送り迎えも結構です。自分のことは全部自分でできますから」
すると熊は、片方の眉を上げてこちらを見てきた。
不愉快そうな顔。けれど残念ながら、わたしはそういう顔が怖くない。孝重郎の怒った時の顔だって相当なもんだったんだから。免疫は十分ついているのだ。
「この家の家賃は?」
「……は?」
一瞬問われた意味がわからなかった。
「この家の家賃だよ。お前が払ってんのか? 生活費も全部?」
「それは……違いますけど」
生活費は月々樋口の家から一定量が振り込まれることになっている。それにこのアパートはウメの持ち家だ。管理人のトメ乃さんの好意で住まわせてもらっている。
「なら全部自分でできるとか言うんじゃねぇよ。一人で生きてるんじゃねぇってことを自覚しろ」
熊は静かな声でそう言うと、再び食事を開始した。
親には子供を養育する義務がある。樋口の家からお金を貰うのは当然だ。
そりゃあなるべく頼りたくないから質素な生活を心がけているし、バイトだってしようと思っていた。そもそもお前みたいなボンボンに言われたくない。この家だって、もともとはウメと二人暮らししていた家なのだ。孝重郎と家を出ようとなった時、住み慣れた家に帰りたいと言ったわたしに孝重郎も賛同してくれた。
そう怒鳴りつけようと思ったわたしの言葉は、結局喉元から先には出てこなかった。
しばらく大きく息を吸いゆっくり吐くということを繰り返し、なんとか冷静な自分を取り戻そうとする。熊が黙ってご飯を食べ続けているので、わたしももそもそと丼を口に運んだ。
駄目だ。
こいつは、本当に駄目だ。
わたしは思った。
こいつは、あまりにずかずかとわたしの中に入り込んでくる。
どんなにわたしが両手を突っ張って踏ん張っても意味はない。こいつの歩みを遮ることなんて誰にもできないのだ。
「ごちそうさま」
熊が言ってパチリと箸を置いた音で、はっと我に返った。
「はーうまかった」
熊は両手を後ろ手について天井を見上げる。
「うわ、あそこの染みこっち見てるみてぇ」
「帰ってください」
わたしは短く言った。
まだ親子丼を食べ終わっていなかったけれど、何かに追い立てられるようにそう言った。右手でぎゅっとポケットに入ったスタンガンを掴む。孝重郎、わたしを守って。
そう願うように思う。
「……」
その時のわたしがどんな顔をしていたのかわからない。
けれど熊男は、ふいに真面目な顔でこちらを見返してきた。
あの時と同じだ。
ローファーをドブに落とした時。それに、ゲームセンターでもそうだった。
わたしを暴く目。
まるでどこも汚れていないかのような双眸。
ああ。
そうか。
その時わたしは唐突に理解した。
けれどすぐにその時理解したことを箱の中に押し込めてしっかりと蓋をして心臓の奥に隠した。
「帰ってください」
わたしはもう一度言った。
すると熊はふぅと息を吐くと、「わかったよ」と言って立ち上がった。
熊との硬直状態が解けたことで、ほっと安堵する。ああ、これでもう大丈夫だ。
奴はご飯つぶ一つ残っていない丼を折りたたみ式のテーブルの上に置いたまま、手ぶらで玄関に向かった。
「あ、そうだ」
そして靴を吐いたところで声を上げる。
「生徒手帳」
熊はポケットからわたしの生徒手帳を出してみせた。
ああ昼間この熊男を助け出そうなんて仏心を出さなければこんな目に遭うこともなかったのに。そう憎々しく思いながら、立ち上がって玄関先に行く。
ありがとうございます、と言うのも変だなと思ってわたしは無言で熊の手にある生徒手帳を取ろうとした。
すると突然反対側の熊の腕がぐんと伸びて、差し出したわたしの手首を掴んで引っ張ってきた。
「っ!」
こける!
と思ったがそうはならなかった。
いつの間にか、唇を柔らかい感触が覆っている。何かに腰の部分が締めつけられている。右手は熊の手の中だ。
わたしが状況を理解するのに必要だった時間がいったいどれほどだったのかはわからない。けれどとにかく、わたしは自分が何をされているのか理解するとすぐに靴下のままの足で目の前の男の脚を蹴った。
「って!」
攻撃はうまく当たったようで、唇が離れ拘束が緩む。
その隙にわたしは身を乗り出し扉を開けると、(もちろん鍵は開けっ放しだった)げしっともう一度熊を足蹴にして部屋から追い出した。
「おわっ……と」
廊下に転がすくらいの勢いで蹴ったつもりだったが、熊の野郎はなんとかバランスを保って尻餅をつくことなく外に出る。
その顔をこの上なく冷たく睨みつけながら、わたしは吐き捨てた。
「死ね!」
そしてガン! と戸枠が悲鳴を上げるような勢いで扉を閉める。
「……」
頭の中が嵐のようになっている。
奪われた。
強く、そう思った。
ぼろぼろと何かが目から零れ落ちた。
まだ唇には生暖かい感触が残っている。
眼鏡を外し、それをぐいと乱暴に拭った。
孝重郎。
わたしは彼の名を呼んだ。
孝重郎。
今すぐ来て。
わたしを抱きしめて。
円、と名前を呼んで。
そう叫ぶようにして何度も願ったが、結局孝重郎は現れなかった。
そのことが、皮膚の外側を覆う空気の膜を震わせた。
「まぁまぁいいからちょっと家にいれろや」
ヤ、ヤクザ! ヤクザのものいいだこれは! まー君たすけてー!
「嫌ですよ! 女子の一人暮らしですよここは。非常識な!」
「いいから入れろって」
「帰ってください!」
思い切りノブを引っ張って扉を閉めようとしたわたしは、けれどその扉がガツンと音を立てて何かに引っかかったので青ざめた。
なんと熊が脚をねじこんできている!
ぎゃー!
「ちょ、何してんですか!」
「いってえなぁお前」
「け、警察呼びますよ!」
「ほお? そんなこと言っていいのか?」
熊はポケットから何かを取り出すと、扉の隙間に持ってきてひらひらとさせた。
生徒手帳だ。
たぶん、わたしの。
あれに住所も書いてある。熊はそれを見ながらここへ来たんだろう。
「なくしたことにするんで別にいいです」
どうせ去年からずーっとポケットの中に入っててその存在すら忘れてたくらいなんだから。
「ほー。えーと、なになに? 八木原円、血液型A型、へぇお前九月生まれなのか。なになに? バスト八十……」
「ぎゃああああ!」
「うるせぇな。ご近所迷惑になるだろ」
「そんなこと生徒手帳に書いてあるわけないだろ!」
「は? お前知らねぇの? 入学した時に健康診断あっただろ? あの時に身体データは全部生徒手帳に書き込まれるんだぞ」
……そ、そうなのか!?
生徒手帳なんて一回も開いたことないから知らなかった……! そんな個人情報の詰まった機密書類だったなんて!
「か、返せ!」
「なら部屋に入れろ」
「なんでだよ!」
「いいからほら、もう観念しろって。な? 別になんもしねぇから」
「……」
わたしは熊を睨みつけた。
何もしないのならなぜ部屋に入る必要があるというのだ。くそ。この変態熊め! さっきの動悸はやっぱりただの神経伝達ミスだ。ああ、わたしの動揺も返せ!
「……すぐ帰ってくださいよ」
しぶしぶそう言うと、熊はにっこりと無邪気に笑ってようやく扉に挟んでいた脚を引いた。一度扉を閉めて、チェーンに手をかけながらしばし逡巡する。
よく考えろ。
本当に家に入れていいのか、あれ?
熊だよ熊。猛獣だよ。
ぐわっと噛み付かれただどうしよう。
そう思ったわたしはふと思いついて部屋の中に戻ると、隅に置いてある収納棚から小ぶりな機械を取り出した。スタンガンだ。昔孝重郎が護身用にと渡してくれた。
それをいそいそと制服のポケットに入れる。
うーん、ちょっとぽっこりしてるけどまぁばれないだろう。
よし、これで安心!
「おい、まだかよ」
扉の向こうから熊が急かす。
「今開けますよ!」
わたしは言ってチェーンを外した。そしてガチャリと再び扉を開ける。
するとにやにやと笑う熊が視界に入った。
「……さぁ、返してください」
熊の手はポケットに入れられていて、生徒手帳は見えない。制服姿のままではあるが、相変わらず手ぶらのようだ。
奴はつと差し出したわたしの手を無視して、ぐいとわたしを押しのけるとずかずかと部屋に入ってきた。
「へー、結構綺麗にしてんじゃねぇか」
「返せよ!」
「まぁ落ち着けって。お前、夕飯は? まぁその格好じゃまだ食べてねぇよな。こないだの鶏肉まだあんのか?」
「……ありますけど」
「じゃあ唐揚げにしてくれ」
「やだよ!」
なんでお前のために揚げ物なんて面倒臭いことをしなければならないんだ!
「仕方ねぇなぁ。親子丼でいいよ」
「一昨日食べた」
「俺は一昨日フォアグラのテリーヌだった」
し、ね!
この時わたしは本当に心からそう思った。格差社会は滅亡すればいいのに。
しかし熊はそんな怨念のこもった視線に気付くことなく、図々しくずかずかと畳の敷いてある部屋に入るとどかりとそこに腰を降ろした。
「なぁ、テーブルねぇの?」
「……そこに立てかけてあります」
「なぁ、なんで布団出てんの? しかもぐちゃぐちゃ」
「……」
わたしはなんだかどっと疲れてしまった。
かくなる上は一刻も早く熊には満足してもらってお帰りいただいた方がいいだろう。さいわい鶏肉も卵も玉ねぎもまだ冷蔵庫に入っている。
深くため息をついたわたしは、熊様ご所望のお供え物を作るため、冷蔵庫を開けた。
……ああ、せめて制服着替えたいんだけどな……。
けれど堂々と覗きそうな熊がいる場所で、着替える気にはならない八木原円であった。
トホホ。
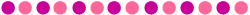
「はい、どうぞ」
「おー。うまそうじゃねぇか」
熊に孝重郎の箸を使わせる気は毛の先ほどもなかったので、わたしはたまたまあった割り箸を出した。(なかったら手で食えって言ってやったのに。ちっ)熊は割り箸を持って「いただきます」とお行儀よく言って、パシ、と小気味いい音を立てて箸を割るとわたしが作った親子丼をぱくぱく食べた。
「……」
熊の正面に座って自分の箸で親子丼を食べながら、わたしは少し驚いていた。
庶民が作った庶民的丼を左手に割り箸を右手に持っているというのに、熊の食事の所作はどことなく上品だ。てっきり体育会系男子のようにご飯を掻き込むんだと思ってたのに、一口一口きちんと味わっている感じがする。
思わすじーっと見入っていたわたしと目が合うと、熊はまたあの子供のような笑顔を見せた。
「うめぇじゃねぇか」
うぐ。
と喉に何かが詰まったような感覚がしたので、慌てて水を飲む。
「お前どれくらい一人暮らししてんの?」
「……一年です」
一人暮らしなら一年だ。
「ふうん。二人暮らしはどれくらいしてたんだ?」
そう問われてわたしはぎょっとした。
え? そんなことまで生徒手帳って書いてあるの?
すると熊はにやりと笑って答える。
「この部屋にゃお前の匂いが染み付いてる。一年だけ住んでたわけじゃねぇだろ? 三人以上住むには手狭だ。だから一年以上前は二人暮らしだった。違うか?」
「……」
なにこいつ怖いんだけど。匂い? なのそれ。本当に獣なの?
「……綾小路先輩には関係ないですよね?」
「ああないね。でも俺はお前に興味がある」
「迷惑です」
「まぁそう言うなって」
魔王の言葉が蘇る。
『玄は、純粋に新しいおもちゃとして、君を気に入っているんだ』
おもちゃ? 冗談じゃない。
わたしは誰かのおもちゃなんかになる気は一切ないんだ。
そう頭の中で悪態をつくと、意を決して切り出す。
「あのですね、綾小路先輩。本当に全部迷惑なんです。マド部とかいう活動もやめてください。送り迎えも結構です。自分のことは全部自分でできますから」
すると熊は、片方の眉を上げてこちらを見てきた。
不愉快そうな顔。けれど残念ながら、わたしはそういう顔が怖くない。孝重郎の怒った時の顔だって相当なもんだったんだから。免疫は十分ついているのだ。
「この家の家賃は?」
「……は?」
一瞬問われた意味がわからなかった。
「この家の家賃だよ。お前が払ってんのか? 生活費も全部?」
「それは……違いますけど」
生活費は月々樋口の家から一定量が振り込まれることになっている。それにこのアパートはウメの持ち家だ。管理人のトメ乃さんの好意で住まわせてもらっている。
「なら全部自分でできるとか言うんじゃねぇよ。一人で生きてるんじゃねぇってことを自覚しろ」
熊は静かな声でそう言うと、再び食事を開始した。
親には子供を養育する義務がある。樋口の家からお金を貰うのは当然だ。
そりゃあなるべく頼りたくないから質素な生活を心がけているし、バイトだってしようと思っていた。そもそもお前みたいなボンボンに言われたくない。この家だって、もともとはウメと二人暮らししていた家なのだ。孝重郎と家を出ようとなった時、住み慣れた家に帰りたいと言ったわたしに孝重郎も賛同してくれた。
そう怒鳴りつけようと思ったわたしの言葉は、結局喉元から先には出てこなかった。
しばらく大きく息を吸いゆっくり吐くということを繰り返し、なんとか冷静な自分を取り戻そうとする。熊が黙ってご飯を食べ続けているので、わたしももそもそと丼を口に運んだ。
駄目だ。
こいつは、本当に駄目だ。
わたしは思った。
こいつは、あまりにずかずかとわたしの中に入り込んでくる。
どんなにわたしが両手を突っ張って踏ん張っても意味はない。こいつの歩みを遮ることなんて誰にもできないのだ。
「ごちそうさま」
熊が言ってパチリと箸を置いた音で、はっと我に返った。
「はーうまかった」
熊は両手を後ろ手について天井を見上げる。
「うわ、あそこの染みこっち見てるみてぇ」
「帰ってください」
わたしは短く言った。
まだ親子丼を食べ終わっていなかったけれど、何かに追い立てられるようにそう言った。右手でぎゅっとポケットに入ったスタンガンを掴む。孝重郎、わたしを守って。
そう願うように思う。
「……」
その時のわたしがどんな顔をしていたのかわからない。
けれど熊男は、ふいに真面目な顔でこちらを見返してきた。
あの時と同じだ。
ローファーをドブに落とした時。それに、ゲームセンターでもそうだった。
わたしを暴く目。
まるでどこも汚れていないかのような双眸。
ああ。
そうか。
その時わたしは唐突に理解した。
けれどすぐにその時理解したことを箱の中に押し込めてしっかりと蓋をして心臓の奥に隠した。
「帰ってください」
わたしはもう一度言った。
すると熊はふぅと息を吐くと、「わかったよ」と言って立ち上がった。
熊との硬直状態が解けたことで、ほっと安堵する。ああ、これでもう大丈夫だ。
奴はご飯つぶ一つ残っていない丼を折りたたみ式のテーブルの上に置いたまま、手ぶらで玄関に向かった。
「あ、そうだ」
そして靴を吐いたところで声を上げる。
「生徒手帳」
熊はポケットからわたしの生徒手帳を出してみせた。
ああ昼間この熊男を助け出そうなんて仏心を出さなければこんな目に遭うこともなかったのに。そう憎々しく思いながら、立ち上がって玄関先に行く。
ありがとうございます、と言うのも変だなと思ってわたしは無言で熊の手にある生徒手帳を取ろうとした。
すると突然反対側の熊の腕がぐんと伸びて、差し出したわたしの手首を掴んで引っ張ってきた。
「っ!」
こける!
と思ったがそうはならなかった。
いつの間にか、唇を柔らかい感触が覆っている。何かに腰の部分が締めつけられている。右手は熊の手の中だ。
わたしが状況を理解するのに必要だった時間がいったいどれほどだったのかはわからない。けれどとにかく、わたしは自分が何をされているのか理解するとすぐに靴下のままの足で目の前の男の脚を蹴った。
「って!」
攻撃はうまく当たったようで、唇が離れ拘束が緩む。
その隙にわたしは身を乗り出し扉を開けると、(もちろん鍵は開けっ放しだった)げしっともう一度熊を足蹴にして部屋から追い出した。
「おわっ……と」
廊下に転がすくらいの勢いで蹴ったつもりだったが、熊の野郎はなんとかバランスを保って尻餅をつくことなく外に出る。
その顔をこの上なく冷たく睨みつけながら、わたしは吐き捨てた。
「死ね!」
そしてガン! と戸枠が悲鳴を上げるような勢いで扉を閉める。
「……」
頭の中が嵐のようになっている。
奪われた。
強く、そう思った。
ぼろぼろと何かが目から零れ落ちた。
まだ唇には生暖かい感触が残っている。
眼鏡を外し、それをぐいと乱暴に拭った。
孝重郎。
わたしは彼の名を呼んだ。
孝重郎。
今すぐ来て。
わたしを抱きしめて。
円、と名前を呼んで。
そう叫ぶようにして何度も願ったが、結局孝重郎は現れなかった。
そのことが、皮膚の外側を覆う空気の膜を震わせた。