ex2.行武王治の親友
Open Menu
綾小路玄という男以上に自分勝手な人間を、それまで俺は見たことがなかった。
面白いものを見つければ周囲に関係なくちょっかいを出し、気に入らなければ相手構わず足蹴にする。揺るがない自信と他人を惹き付けるセンス。そして完璧な家柄と恵まれた体格。
人間なら大小なりとも誰もが持っているだろう暗い部分が男には欠片もなく、その前に立った俺は苛立ちや劣等感を抱くのを越えてただ感歎したのだ。
そして思った。
この男の側にいれば、面白いものが見られるだろうと。
『すごく迷惑です』
あの日、そう答えた少女を見ながら俺はほくそ笑んだ。
『やっぱり玄が君を気に入るのもわかるよ、円ちゃん』
ああやはり、俺が思っていた通りだ。
玄の側にはいつも面白いものが転がっている。
勝てない喧嘩を売ってくる不良達。めげるということを知らない同級生。
そして不幸なこの少女。
八木原円。
地味で黒髪眼鏡の不運な彼女がもたらすものを、俺は楽しみに見守ろう。
粗暴で傲慢な親友の隣で。
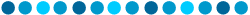
国語のタニセンが腹痛のため早退したとかで、六限目は自習だった。
まだ受験を遠い未来の話だと信じている二年生の教室の中では、真面目に自習している生徒はほんの一握りだけだ。そしてもちろん俺も、国語の教科書の代わりに読みかけの文庫本を取り出して読書に励んでいた。
ちょうど孤島の中の館で第二の殺人が起きたその時、ガラリとすぐ横の扉が開いてわが二年D組の副担任である崎村が顔をのぞかせた。教師の中でも若く融通のきく崎村は、自習中というにはいささか騒がしい教室内をざっと見渡し「うるさいぞ。静かにしろ」と表面的な叱責を口にしただけで、手近にいた俺を見た。
「綾小路はどうした」
「知りません」
俺はとぼけて答えた。
実のところ心当たりはあったのだが、それをわざわざ教えてやる義理もない。
玄は五限目が終ってすぐ教室から姿を消していた。あの自由な男が授業をさぼったり学校を抜け出すのは今に始まったことではなく、教室内の誰も綾小路玄の不在を不思議にも思っていないようだ。そしてそれは副担任の崎村にしても同じことで、彼は呆れたように眉を上げてから「綾小路に電話がきてるんだ」と言った。
「緊急の電話らしいんだが……」
その時俺が真っ先に思い浮かべたのは玄の家だった。
綾小路家は由緒正しい金持ちだ。その屋敷が建つ敷地は一般的な俺の家がいくつも入りそうに広く、当然ながら執事や使用人や運転手と呼ばれる生き物が働いている。俺は何度か綾小路家に出入りしていて、運転手の鈴木さんとも顔見知りだった。
崎村がなおも何か言いたげに俺の方を見てくるので、仕方なく手に持っていた本をぱたりと閉じた。俺が玄といつもつるんでいるということは、教師にも知れている。
「わかりました。玄に伝えておきますよ」
「すまないな、助かる。頼んだぞ」
崎村はそう言うと、まだ若干騒がしい室内を一瞥してから教室を出て行った。
電話が来ているということは事務室だろう。
俺は椅子から立ち上がった。
「なんだよ、行武。今サッキーに何頼まれたん?」
一列挟んで奥側の席にいる三宅が声を投げかけてくる。見れば三宅は前の席の成島と二人で将棋に興じているようだ。ちなみに三宅は確かサッカー部だ。そして成島は囲碁部。あの将棋盤は、この教室の掃除用具入れにずっと放置されていたものだろう。誰の物かも不明である。
「ちょっと野暮用」
説明が面倒だと感じた俺は、そうとだけ答えて席を立った。
中学時代は腫れ物のように扱われていた俺と玄だが、高校に入ってからは幾分大人しい学生生活を送っているおかげかうまくクラスにもなじめている。喧嘩も校内ではほとんどしていない。
まぁ、俺達に喧嘩を売ってくるような人種が校内にいないというだけの話だ。
この学区内のそういう輩はほとんどが町田北高校といういわゆる不良高校に進学している。わが永嵐高校は一応偏差値70の進学校なので、中学時代喧嘩に明け暮れていた馬鹿共はまず進学先として選ばないのだ。
自慢ではないが、そんな中俺と玄が永嵐高校に入学できたのは正真正銘実力だ。
ただし玄の場合は動物的な直感力による天才で、俺の場合は日頃の努力の成果だった。
勉強は嫌いじゃない。ただ人より少し度胸があって喧嘩の才能があり目立つ容姿を持っていたので、中学時代は魔王などと呼ばれることになったというだけだ。
授業中でしんとした廊下を歩き、俺は事務室に向かった。
玄はおそらく校外に出ている。この時間に教室にいない場合は、近くの本屋で漫画の立ち読みをしている可能性がすこぶる高い。なので俺は代わりにその緊急の電話とやらを取るつもりだった。親が倒れたとかそういう話だったら、本屋まで報せにいけばいい。
「すいません、二年の綾小路に電話がきてるって聞いたんですけど」
がらりと事務室の扉を開けて事務のおっさんに声をかける。
おっさんはこちらをちらりと見ることもせずに、事務室の受付前に置いてある電話の方にくいと顎を傾けた。このおっさんはいつもこうなのだ。愛想というものをどこかに置き忘れてきたらしい。なぜこんなおっさんをこの来賓出入り口に配置しているのか、俺はいつも疑問だった。保護者からクレームとかがこないのだろうか。
俺は保留のランプがついている薄汚れた電話機から受話器を取った。
「代わりました」
『綾小路先輩!?』
電話口から聞こえてきたのは予想外に若い女性の声だった。
『あの、急いで来てください! うちの弟と円が、不良に捕まって……! たぶん北高の人達だと思うんですけど、弟がいるから警察には行けなくて……!』
「……ええと、君、名前は?」
動揺している様子の女を宥めるために、俺はことさらゆっくりと名前を問うた。
『清水です! 円と同じクラスの!』
俺は先日円ちゃんと二人で化学準備室に顔を出しに来ていた女生徒を思い出した。うちの中学のミスだったとかいう子だ。
円ちゃんが頭に辞書をぶつけられて早退したという話は聞いていたが、まだ授業が行われているこの時間になぜこの子も校外にいるのだろう。まぁどうでもいいけど。
「ああ、はい。清水さんね。それで、円ちゃんが北高の不良に捕まったって?」
『そうなんです! 円、私のことだけ逃がしてくれて……。早く助けに来てください!』
なるほど。ドラマのような話じゃないか。
俺は思わず噴き出しそうになったのを必死でこらえなくてはならなかった。
どういう理由でそういうことになったのかわからないが、八木原円というのは本当に運のない少女だ。暴力とは縁のなさそうなあんな黒髪眼鏡の女子高生が、なんで町田北高の不良に絡まれるなどという展開になるのだろうか。非常に興味深い。
清水なんとかちゃんが玄に助けを求めてきた理由はなんとなく理解できた。彼女は俺達と同じ中学なのだ。つまり俺と玄の悪名を知っている。それなら彼女が、町田北高の不良から友人を奪還するに適当な相手として、玄を思いついたのは不思議でもなんでもない。
「……とりあえず落ち着いて? 今どこなの?」
笑いをなんとか噛み殺した俺は、声音だけは真面目に聞こえるように問うた。
『ええと、キムラパンの横の……』
「円がなんだって?」
清水なんとかちゃんの言葉は途中で俺の耳から離れた。正確には、肩をぐいと掴まれたので受話器から耳が離れたのだ。
「今の円っていうのは八木原円のことだろう? 不良に捕まった?」
そこにいたのは三年の樋口という名の生徒会書記だった。
そう、八木原円の腹違いの兄であり先日誰もいない生徒会室でその義理の妹を押し倒していた樋口舜先輩だ。
うん。あれは衝撃的な場面だったな。衝撃的すぎてすぐ玄にことのあらましを話してしまったほどだ。俺の話を聞いた玄は「ふーん」とそっけなく答えただけだったが、面白くないと思っていることはすぐにわかった。玄は自分のおもちゃに他人の手がつくことを嫌うからだ。
「ええと、樋口先輩?」
俺は受話器を手で塞ぎ、こちらの声が聞こえないようにした。
三年生といえど授業中のはずだが、手に持っているプリントの束を見るに教師から持ってくるよう頼まれたのだろう。なんていいタイミングでこの前を通りかかったんだ。
「今電話中なんです。邪魔しないでいただけますか?」
「八木原円のことなら、俺はあいつの兄で校内では保護者だ。何があったのか話せ」
ずいぶんと偉そうな言い方だ。
少しカチンときて眉を上げたが、考えるより先に手が出てしまっていた魔王時代とは違う。一瞬の思考の結果、より面白い状況を呼び込む展開を、俺は選ぶことにした。
受話器を塞いでいた手を離し、清水なんとかちゃんに再度問う。
「えっとごめんね。キムラパンの横のなんだって?」
『キムラパンの横の路地を入ってまっすぐ行ったら左手にあるビルの四階です! 橋本税理士事務所っていう看板が出てるビルで……ええと』
「キムラパンの横の路地、左手の橋本税理士事務所が入ってるビルの四階ね?」
俺は樋口先輩を見ながらそう繰り返した。
するとは樋口先輩は、持っていたプリントの束を「これを古賀先生に渡しておいてくれ」と俺に押し付けて来賓出入り口から飛び出した。
もちろん上履きのままだ。俺はぴゅうと口笛を吹く。
どうやら樋口先輩が円ちゃんになんらかの特別な感情を持っていることは確実なようだ。これはますます面白くなりそうだぞ、と俺はほくそ笑むと、『綾小路先輩! 聞こえてますか?』と電話口で叫ぶ少女に優しい声で言った。
「聞こえてるよ。大丈夫。すぐに行くから君はどこかに隠れていて。あ、ちなみに俺は玄じゃなくて、二年の行武だよ」
『……えっ! 行武先輩……!?』
「じゃあね」
面白い場面を見逃してはなるまいと、俺はすぐに電話を切ると目の前の受付の窓を開け、そこにいたおっさんの前に樋口先輩から預かったプリントを投げ出した。
「すいませんけど緊急事態なんでこの書類を古賀先生に渡しておいてください」
そう言い捨てると、反論を受ける前に受付の窓をぴしゃりと閉めて靴箱のある昇降口へと駆ける。樋口先輩と違って、俺は上履きのまま外に出るなんてダサいことをするのはごめんだからだ。
靴を履き替え、自転車置き場に自転車を取りに行く。俺は自転車通学ではないが、たいてい鍵をかけていない自転車の一台や二台あるはずだ。案の定盗んでくださいとばかりに無防備な灰色のママチャリを見つけると、それに飛び乗って校門へ向かった。
しかし俺はその直後に、既に自分が出遅れてしまったことを知った。
自転車置き場から出て校舎を曲がるとすぐ校門が見えるのだが、そこに五人の男が立っているのを見つけたからだ。
一人は樋口先輩で、もう一人は今まさに俺が探しに行こうとしていた玄だった。どうやら立ち読みを終えて学校に戻ってきたところらしい。そして校門前に停められた車の周りに、見知らぬ三人の男が立っている。……奇妙な取り合わせだな。サラリーマンと……大学生か? それにあの柄シャツはどう見てもヤクザなんだが。
その奇妙な三人は俺が校門前にたどり着く前に慌ただしく車に乗り込むと、何故か樋口先輩もその車の後部座席に滑り込んだ。そして車がキュルルと音を立てて発進していった後に玄だけが残る。
「玄!」
自転車から下りて名を呼ぶと、玄が振り向いた。
「おう」
「お前、話聞いたのか? 円ちゃんが……」
「ああ、北高の奴らに拉致されたって?」
俺にはどうして玄がこんなにも冷静な様子でここに突っ立っているのかわからなかった。もしかしてもう円ちゃんに飽きてしまったというのだろうか。マド部なんて部活まで作ったのに?
「助けに行かないのか?」
「大の大人が三人と、役に立つのか知らねぇが生徒会の奴まで一緒に行ったんだから俺が行く必要ねぇだろ」
「だけど……」
「それよりそのチャリ貸せ」
「は?」
「ちょっと行くところができた」
そう言うと、綾小路玄は俺の手から(誰のとも知れない)自転車を半ば強引に奪って再び校門から出て行った。曲がったのは左で、車とは逆方向だ。つまり円ちゃんを助けに行ったわけではないらしい。
「……なんだよー」
俺は少々がっかりした。
玄はもっと円ちゃんに執着していると思っていたのだが、須磨の時と同じようにただのおもちゃの一つだったようだ。こんなに簡単に飽きてしまうなんて。
これではまったく面白くない。
「……」
あてが外れた俺は、とりあえず校舎に戻ることにした。
玄の言う通り、樋口先輩達が行ったのならわざわざ自分が助けにいく必要はないだろう。なんだかよくわからないが目立ちそうな大人三人も一緒だったし。
踵を返しなんとなく顔を上げると、抜けるような青空が広がっている。心地のいい春の風が前髪を揺らした。
自分の予感は当たる方だと自負していたが、今回に限っては外れたらしい。
こういう日は売られた喧嘩を片っ端から買って憂さ晴らしをするとすっきりするのだが、この高校では喧嘩を売ってくる人間さえいないので、とりあえず教室に戻って孤島の館で起きた殺人事件の行く末を見守ろうと思った俺だった。
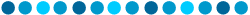
さて、もちろん話はここで終わらない。
その後、円ちゃんの身に何が起きたのか、玄が何をしに行ったのかを俺は遅れて知ることになる。
そして改めて思うのだ。
綾小路玄という男は特別なのだと。
俺の思考の斜め上をいく男なのだと。
同時にわずかな驚きと予感も覚えた。
彼女ももしかしたら、特別なのかもしれない。
粗暴で傲慢で特別な俺の親友を変えた、地味で黒髪眼鏡の不運な女。
八木原円。
うん。
どうやこの高校生活、思っていたより面白くなりそうである。
面白いものを見つければ周囲に関係なくちょっかいを出し、気に入らなければ相手構わず足蹴にする。揺るがない自信と他人を惹き付けるセンス。そして完璧な家柄と恵まれた体格。
人間なら大小なりとも誰もが持っているだろう暗い部分が男には欠片もなく、その前に立った俺は苛立ちや劣等感を抱くのを越えてただ感歎したのだ。
そして思った。
この男の側にいれば、面白いものが見られるだろうと。
『すごく迷惑です』
あの日、そう答えた少女を見ながら俺はほくそ笑んだ。
『やっぱり玄が君を気に入るのもわかるよ、円ちゃん』
ああやはり、俺が思っていた通りだ。
玄の側にはいつも面白いものが転がっている。
勝てない喧嘩を売ってくる不良達。めげるということを知らない同級生。
そして不幸なこの少女。
八木原円。
地味で黒髪眼鏡の不運な彼女がもたらすものを、俺は楽しみに見守ろう。
粗暴で傲慢な親友の隣で。
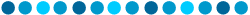
国語のタニセンが腹痛のため早退したとかで、六限目は自習だった。
まだ受験を遠い未来の話だと信じている二年生の教室の中では、真面目に自習している生徒はほんの一握りだけだ。そしてもちろん俺も、国語の教科書の代わりに読みかけの文庫本を取り出して読書に励んでいた。
ちょうど孤島の中の館で第二の殺人が起きたその時、ガラリとすぐ横の扉が開いてわが二年D組の副担任である崎村が顔をのぞかせた。教師の中でも若く融通のきく崎村は、自習中というにはいささか騒がしい教室内をざっと見渡し「うるさいぞ。静かにしろ」と表面的な叱責を口にしただけで、手近にいた俺を見た。
「綾小路はどうした」
「知りません」
俺はとぼけて答えた。
実のところ心当たりはあったのだが、それをわざわざ教えてやる義理もない。
玄は五限目が終ってすぐ教室から姿を消していた。あの自由な男が授業をさぼったり学校を抜け出すのは今に始まったことではなく、教室内の誰も綾小路玄の不在を不思議にも思っていないようだ。そしてそれは副担任の崎村にしても同じことで、彼は呆れたように眉を上げてから「綾小路に電話がきてるんだ」と言った。
「緊急の電話らしいんだが……」
その時俺が真っ先に思い浮かべたのは玄の家だった。
綾小路家は由緒正しい金持ちだ。その屋敷が建つ敷地は一般的な俺の家がいくつも入りそうに広く、当然ながら執事や使用人や運転手と呼ばれる生き物が働いている。俺は何度か綾小路家に出入りしていて、運転手の鈴木さんとも顔見知りだった。
崎村がなおも何か言いたげに俺の方を見てくるので、仕方なく手に持っていた本をぱたりと閉じた。俺が玄といつもつるんでいるということは、教師にも知れている。
「わかりました。玄に伝えておきますよ」
「すまないな、助かる。頼んだぞ」
崎村はそう言うと、まだ若干騒がしい室内を一瞥してから教室を出て行った。
電話が来ているということは事務室だろう。
俺は椅子から立ち上がった。
「なんだよ、行武。今サッキーに何頼まれたん?」
一列挟んで奥側の席にいる三宅が声を投げかけてくる。見れば三宅は前の席の成島と二人で将棋に興じているようだ。ちなみに三宅は確かサッカー部だ。そして成島は囲碁部。あの将棋盤は、この教室の掃除用具入れにずっと放置されていたものだろう。誰の物かも不明である。
「ちょっと野暮用」
説明が面倒だと感じた俺は、そうとだけ答えて席を立った。
中学時代は腫れ物のように扱われていた俺と玄だが、高校に入ってからは幾分大人しい学生生活を送っているおかげかうまくクラスにもなじめている。喧嘩も校内ではほとんどしていない。
まぁ、俺達に喧嘩を売ってくるような人種が校内にいないというだけの話だ。
この学区内のそういう輩はほとんどが町田北高校といういわゆる不良高校に進学している。わが永嵐高校は一応偏差値70の進学校なので、中学時代喧嘩に明け暮れていた馬鹿共はまず進学先として選ばないのだ。
自慢ではないが、そんな中俺と玄が永嵐高校に入学できたのは正真正銘実力だ。
ただし玄の場合は動物的な直感力による天才で、俺の場合は日頃の努力の成果だった。
勉強は嫌いじゃない。ただ人より少し度胸があって喧嘩の才能があり目立つ容姿を持っていたので、中学時代は魔王などと呼ばれることになったというだけだ。
授業中でしんとした廊下を歩き、俺は事務室に向かった。
玄はおそらく校外に出ている。この時間に教室にいない場合は、近くの本屋で漫画の立ち読みをしている可能性がすこぶる高い。なので俺は代わりにその緊急の電話とやらを取るつもりだった。親が倒れたとかそういう話だったら、本屋まで報せにいけばいい。
「すいません、二年の綾小路に電話がきてるって聞いたんですけど」
がらりと事務室の扉を開けて事務のおっさんに声をかける。
おっさんはこちらをちらりと見ることもせずに、事務室の受付前に置いてある電話の方にくいと顎を傾けた。このおっさんはいつもこうなのだ。愛想というものをどこかに置き忘れてきたらしい。なぜこんなおっさんをこの来賓出入り口に配置しているのか、俺はいつも疑問だった。保護者からクレームとかがこないのだろうか。
俺は保留のランプがついている薄汚れた電話機から受話器を取った。
「代わりました」
『綾小路先輩!?』
電話口から聞こえてきたのは予想外に若い女性の声だった。
『あの、急いで来てください! うちの弟と円が、不良に捕まって……! たぶん北高の人達だと思うんですけど、弟がいるから警察には行けなくて……!』
「……ええと、君、名前は?」
動揺している様子の女を宥めるために、俺はことさらゆっくりと名前を問うた。
『清水です! 円と同じクラスの!』
俺は先日円ちゃんと二人で化学準備室に顔を出しに来ていた女生徒を思い出した。うちの中学のミスだったとかいう子だ。
円ちゃんが頭に辞書をぶつけられて早退したという話は聞いていたが、まだ授業が行われているこの時間になぜこの子も校外にいるのだろう。まぁどうでもいいけど。
「ああ、はい。清水さんね。それで、円ちゃんが北高の不良に捕まったって?」
『そうなんです! 円、私のことだけ逃がしてくれて……。早く助けに来てください!』
なるほど。ドラマのような話じゃないか。
俺は思わず噴き出しそうになったのを必死でこらえなくてはならなかった。
どういう理由でそういうことになったのかわからないが、八木原円というのは本当に運のない少女だ。暴力とは縁のなさそうなあんな黒髪眼鏡の女子高生が、なんで町田北高の不良に絡まれるなどという展開になるのだろうか。非常に興味深い。
清水なんとかちゃんが玄に助けを求めてきた理由はなんとなく理解できた。彼女は俺達と同じ中学なのだ。つまり俺と玄の悪名を知っている。それなら彼女が、町田北高の不良から友人を奪還するに適当な相手として、玄を思いついたのは不思議でもなんでもない。
「……とりあえず落ち着いて? 今どこなの?」
笑いをなんとか噛み殺した俺は、声音だけは真面目に聞こえるように問うた。
『ええと、キムラパンの横の……』
「円がなんだって?」
清水なんとかちゃんの言葉は途中で俺の耳から離れた。正確には、肩をぐいと掴まれたので受話器から耳が離れたのだ。
「今の円っていうのは八木原円のことだろう? 不良に捕まった?」
そこにいたのは三年の樋口という名の生徒会書記だった。
そう、八木原円の腹違いの兄であり先日誰もいない生徒会室でその義理の妹を押し倒していた樋口舜先輩だ。
うん。あれは衝撃的な場面だったな。衝撃的すぎてすぐ玄にことのあらましを話してしまったほどだ。俺の話を聞いた玄は「ふーん」とそっけなく答えただけだったが、面白くないと思っていることはすぐにわかった。玄は自分のおもちゃに他人の手がつくことを嫌うからだ。
「ええと、樋口先輩?」
俺は受話器を手で塞ぎ、こちらの声が聞こえないようにした。
三年生といえど授業中のはずだが、手に持っているプリントの束を見るに教師から持ってくるよう頼まれたのだろう。なんていいタイミングでこの前を通りかかったんだ。
「今電話中なんです。邪魔しないでいただけますか?」
「八木原円のことなら、俺はあいつの兄で校内では保護者だ。何があったのか話せ」
ずいぶんと偉そうな言い方だ。
少しカチンときて眉を上げたが、考えるより先に手が出てしまっていた魔王時代とは違う。一瞬の思考の結果、より面白い状況を呼び込む展開を、俺は選ぶことにした。
受話器を塞いでいた手を離し、清水なんとかちゃんに再度問う。
「えっとごめんね。キムラパンの横のなんだって?」
『キムラパンの横の路地を入ってまっすぐ行ったら左手にあるビルの四階です! 橋本税理士事務所っていう看板が出てるビルで……ええと』
「キムラパンの横の路地、左手の橋本税理士事務所が入ってるビルの四階ね?」
俺は樋口先輩を見ながらそう繰り返した。
するとは樋口先輩は、持っていたプリントの束を「これを古賀先生に渡しておいてくれ」と俺に押し付けて来賓出入り口から飛び出した。
もちろん上履きのままだ。俺はぴゅうと口笛を吹く。
どうやら樋口先輩が円ちゃんになんらかの特別な感情を持っていることは確実なようだ。これはますます面白くなりそうだぞ、と俺はほくそ笑むと、『綾小路先輩! 聞こえてますか?』と電話口で叫ぶ少女に優しい声で言った。
「聞こえてるよ。大丈夫。すぐに行くから君はどこかに隠れていて。あ、ちなみに俺は玄じゃなくて、二年の行武だよ」
『……えっ! 行武先輩……!?』
「じゃあね」
面白い場面を見逃してはなるまいと、俺はすぐに電話を切ると目の前の受付の窓を開け、そこにいたおっさんの前に樋口先輩から預かったプリントを投げ出した。
「すいませんけど緊急事態なんでこの書類を古賀先生に渡しておいてください」
そう言い捨てると、反論を受ける前に受付の窓をぴしゃりと閉めて靴箱のある昇降口へと駆ける。樋口先輩と違って、俺は上履きのまま外に出るなんてダサいことをするのはごめんだからだ。
靴を履き替え、自転車置き場に自転車を取りに行く。俺は自転車通学ではないが、たいてい鍵をかけていない自転車の一台や二台あるはずだ。案の定盗んでくださいとばかりに無防備な灰色のママチャリを見つけると、それに飛び乗って校門へ向かった。
しかし俺はその直後に、既に自分が出遅れてしまったことを知った。
自転車置き場から出て校舎を曲がるとすぐ校門が見えるのだが、そこに五人の男が立っているのを見つけたからだ。
一人は樋口先輩で、もう一人は今まさに俺が探しに行こうとしていた玄だった。どうやら立ち読みを終えて学校に戻ってきたところらしい。そして校門前に停められた車の周りに、見知らぬ三人の男が立っている。……奇妙な取り合わせだな。サラリーマンと……大学生か? それにあの柄シャツはどう見てもヤクザなんだが。
その奇妙な三人は俺が校門前にたどり着く前に慌ただしく車に乗り込むと、何故か樋口先輩もその車の後部座席に滑り込んだ。そして車がキュルルと音を立てて発進していった後に玄だけが残る。
「玄!」
自転車から下りて名を呼ぶと、玄が振り向いた。
「おう」
「お前、話聞いたのか? 円ちゃんが……」
「ああ、北高の奴らに拉致されたって?」
俺にはどうして玄がこんなにも冷静な様子でここに突っ立っているのかわからなかった。もしかしてもう円ちゃんに飽きてしまったというのだろうか。マド部なんて部活まで作ったのに?
「助けに行かないのか?」
「大の大人が三人と、役に立つのか知らねぇが生徒会の奴まで一緒に行ったんだから俺が行く必要ねぇだろ」
「だけど……」
「それよりそのチャリ貸せ」
「は?」
「ちょっと行くところができた」
そう言うと、綾小路玄は俺の手から(誰のとも知れない)自転車を半ば強引に奪って再び校門から出て行った。曲がったのは左で、車とは逆方向だ。つまり円ちゃんを助けに行ったわけではないらしい。
「……なんだよー」
俺は少々がっかりした。
玄はもっと円ちゃんに執着していると思っていたのだが、須磨の時と同じようにただのおもちゃの一つだったようだ。こんなに簡単に飽きてしまうなんて。
これではまったく面白くない。
「……」
あてが外れた俺は、とりあえず校舎に戻ることにした。
玄の言う通り、樋口先輩達が行ったのならわざわざ自分が助けにいく必要はないだろう。なんだかよくわからないが目立ちそうな大人三人も一緒だったし。
踵を返しなんとなく顔を上げると、抜けるような青空が広がっている。心地のいい春の風が前髪を揺らした。
自分の予感は当たる方だと自負していたが、今回に限っては外れたらしい。
こういう日は売られた喧嘩を片っ端から買って憂さ晴らしをするとすっきりするのだが、この高校では喧嘩を売ってくる人間さえいないので、とりあえず教室に戻って孤島の館で起きた殺人事件の行く末を見守ろうと思った俺だった。
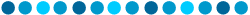
さて、もちろん話はここで終わらない。
その後、円ちゃんの身に何が起きたのか、玄が何をしに行ったのかを俺は遅れて知ることになる。
そして改めて思うのだ。
綾小路玄という男は特別なのだと。
俺の思考の斜め上をいく男なのだと。
同時にわずかな驚きと予感も覚えた。
彼女ももしかしたら、特別なのかもしれない。
粗暴で傲慢で特別な俺の親友を変えた、地味で黒髪眼鏡の不運な女。
八木原円。
うん。
どうやこの高校生活、思っていたより面白くなりそうである。