ex3.綾小路玄の世界
Open Menu
他人にどう見えようが、俺はこの世界を愛している。
青い空と、自動販売機の下に落ちた十円玉。それを拾おうとする小学生と、早朝からひったくりをするおっさん。同じ服を着た同じ年代の少年少女が通う学校と、チョークで白衣を汚した教師。
俺はそのどれもを公平に愛しているし、世界は常に明るく楽しい。
そう。
常に明るく楽しいのだ。
だからあの女に興味を持った。
どうにも運の悪そうなあの女。
冴えない外見のくせに留年していて、入学式では死にかけ、不良に突っかかり眼鏡を割るような女だ。
あの女はきっと、俺とは違う世界を見ているに違いない。
それはどんな世界だろう?
その不運さにも関わらず、決して暗く鬱屈としたものではないはずだ。もしそうなら、あんなにも強い眼差しで俺を見てくるはずがない。
ああ本当に。
世界は明るく楽しい。
あんな興味深い女がいるんだから、生きていることはやめられない。
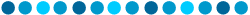
「え? 一人でぼっこぼこにしてきたの?」
箸を右手に持ったまま玄関先に現れた王治は、目をきょとんと丸くした。
どうやらこの匂いからすると行武家の今日の夕食は豚の生姜焼きのようだ。俺の家は合鴨のパイ包み焼きだったが、豚の生姜焼きの方が好きだ。鴨は飽きた。
「王治ー! 玄ちゃんに中入ってもらいなさい! もう一人分ならあるから!」
「え! それ俺が食う分じゃねぇの!」
「うるさい健治! あんたは食いすぎ!」
中からおばさんと、王治の弟の声が聞こえる。
行武家の父親はずいぶんと前に蒸発したらしい。王治と弟の健治はおばさんが女手一つで育てている。彼女は、俺が尊敬する数少ない女性の一人だ。
「入る?」
王治が身体を斜めにして聞いてきたが、
「いや、いい。もう飯は食ったし」
と俺は断った。この団地の外に車も待たせているしな。
「あそ。で、一人でぼっこぼこにしてきたってどういうこと? 怪我してる様子もないけど」
鍵やら印鑑やら蝋燭やら靴べらやらごちゃごちゃといろいろ置かれている玄関に備え付けの靴箱に寄りかかり、王治が言う。
「あ、お前まさか、タイマンの約束があったからあの時自転車でさっさと帰ったわけ? なんで俺も誘わないんだよー」
俺と王治は、中学では不良の間で結構有名だったのだが、実際のところ嬉々として喧嘩に参加していたのは王治の方だった。俺はほぼ付き添い。その証拠に、俺にはあだ名はないが、王治には魔王なんていうあだ名がついた。考えた奴なかなかいいセンスしてるよな。
王治とは小五からの付き合いだが、こいつはその頃からわけのわからない性格だった。
高校に入ったら喧嘩はやめようとか言い出したのもこいつだ。クラスメートに対する口調を変え、一人称さえ『俺』から『僕』に変えたこいつの徹底ぶりは見ていて気持ち悪いくらいだ。
まぁそんなわけのわからん奴だからこそ、こんなに長い事つるんでいられるんだろうと思うけど。
七年だ。
その年月は、親友と呼べる程度には長い。
「いや、そうじゃなくて、八木原円に今後ちょっかいかけんなって言ってきた」
だからこう告げた時、王治の反応はある程度予想できた。
「……はぁ?」
王治は眉を上げて靴箱に寄りかかるのをやめた。
「おいおい、そりゃどういうことだよ。円ちゃん? え? お前、わざわざ円ちゃんのために北高行って、トップの奴ボコってきたわけ?」
「そうだ」
「え? なんで?」
「北高の奴らなら逆恨みで円襲うくらいのことしそうだろ」
「は? なんの逆恨み?」
「今日のことの」
王治は箸を靴箱の上に置いて額に手を当て、「うーん」と唸った。しかしすぐに残念そうな様子で首を振る。
「駄目だ。全然わかんねぇ。てゆうかお前、今日円ちゃんがあの後どうなったか知ってんの?」
なるほど。こいつは不良に拉致られた円がどうなったか確認することもしなかったわけだ。行武王治が優しげな見た目を裏切る冷血な男だということを俺はよく知っていた。
「お前、あの三人のこと知らないのか?」
そして世間知らず。こいつより俺の方がずっと常識を持っているはずだ。
「死神カルテットだよ。いや、死のカルテットだったか? まぁどっちでもいいか。俺らが小学生ん時北高で有名だったじゃねぇか」
「んー。聞いたことあるようなないような……?」
「とにかく、あの三人が行ったなら円を拉致した奴らは紙切れみたいに一蹴されて円は助けられたはずだ」
最初に会った時からどっかで見た顔だと思っていたのだ。八木原円と駅前の定食屋にいた二人の男。
そして家に帰ってから思い出した。
北高で有名だった不良四人組だ。
確かうちの一人はここ数年で死んだとかなんとかいう話を聞いたが……、ああ、だから今日も三人だったのか。しかし円は、あいつらとどういう関係なんだ。本当に予想を裏切る面白い女。
「ええとつまり、北高の奴らが、今日その死神なんとかってやつにボコられた腹いせに円ちゃんにちょっかいかける可能性があるから、先手を打ったってこと?」
王治は人差し指で円を描きながら考えて言った。
「まぁ、そうだな」
「お前が? なんで?」
俺はため息をついた。
今日の王治はいつにも増して理解が遅い。
「マド部の活動を忘れたのか? 『八木原円の不幸の回避とその対処法の研究』」
つまり、俺は円の不幸を前もって回避してやったに過ぎない。
「ああつまり、お前がやってやったことを円ちゃんに教えて恩に着せて嫌がらせするってこと?」
「は? 別に円に言う必要はない。それよりお前には明日、あいつを迎えに行ってやってほしいんだ。そういえば、明日の当番決めてなかっただろ」
「……」
王治は今まで見たことのなかった顔をした。
ものすごいまずい餌を食べさせられた時のうちのドーベルマンみたいな顔だ。
「……お前、自分の言ってることわかってんの?」
「お前こそ、日本語が理解できてるか? 明日はお前が円を迎えに行け」
俺は念のためもう一度言った。
「いや、それはわかってるけどさ……。どうしてお前が行かないんだよ」
「は? その話は最初にしただろ。円が朝大体何時に家を出ると思ってんだ。七時だぞ、七時。その時間俺はまだ寝てる」
俺は低血圧なのだ。
朝は弱い。
円に初めて会った日だって、始業式だからと無理矢理親父に起こされていなければ余裕で遅刻していただろう。そうなれば円にも会っていなかった。うん。縁というのは本当に面白い。
「いやだけど……。うん。まあいいや。俺が明日円ちゃんを迎えに行けばいいんだな? お前はそれを言うためだけに、夜の八時を回ったこの時間に俺んちに来たんだな?」
王治が細かく確認してくる。
「そうだ」
俺は頷いた。
「じゃあ頼んだぞ」
ようやく用件をすませることができたので、「じゃあな」と言って団地の狭い階段を降りる。俺が踊り場を曲がって下の階に降りたところで、ようやく王治ががちゃんと扉を閉めた音がした。
なんかあいつ、最後はすげぇ面白いものを見つけた時みたいな顔してたけど、ちゃんと俺が言ったこと理解してるんだろうな。俺の中を一瞬不安がよぎるが、まぁ長年の付き合いによる信頼というものを信用することにした。
郵便受けが八個並んでいる一階に降りると、小さな花壇の前を通り過ぎて団地の外に出る。
鈴木が運転席に座る車は外灯の灯りが届かないところに停めてあった。
「出していいぞ」
後部座席に乗ると、鈴木に命じる。
「かしこまりました」
鈴木は余計なことは何も聞かないし言わない。優秀な運転手だ。
俺は、今日家に帰ってから鈴木に渡された紙切れのことを思い出した。
八木原円から言付かったのだという。
『私は歩いて帰るけど、鈴木さんに責任はないから。
減俸とかそういうことしたらただじゃおかない。
具体的には、裸で外をうろつく変態趣味があるとか鼻の穴ほじりながらじゃないと用をたせないとかあることないこと学校でいいふらしてやる。 八木原円』
ああ本当に、面白い女。
俺は窓の外の、外灯の少ない住宅街を見ながら笑った
近年稀に見るヒットだ。
こいつはしばらく退屈しないに違いない。
「ずいぶんと、ご機嫌がよろしゅうございますね」
鈴木が言う。
「そうだな。いい夜だ」
俺はそう答えたのだった。
青い空と、自動販売機の下に落ちた十円玉。それを拾おうとする小学生と、早朝からひったくりをするおっさん。同じ服を着た同じ年代の少年少女が通う学校と、チョークで白衣を汚した教師。
俺はそのどれもを公平に愛しているし、世界は常に明るく楽しい。
そう。
常に明るく楽しいのだ。
だからあの女に興味を持った。
どうにも運の悪そうなあの女。
冴えない外見のくせに留年していて、入学式では死にかけ、不良に突っかかり眼鏡を割るような女だ。
あの女はきっと、俺とは違う世界を見ているに違いない。
それはどんな世界だろう?
その不運さにも関わらず、決して暗く鬱屈としたものではないはずだ。もしそうなら、あんなにも強い眼差しで俺を見てくるはずがない。
ああ本当に。
世界は明るく楽しい。
あんな興味深い女がいるんだから、生きていることはやめられない。
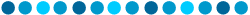
「え? 一人でぼっこぼこにしてきたの?」
箸を右手に持ったまま玄関先に現れた王治は、目をきょとんと丸くした。
どうやらこの匂いからすると行武家の今日の夕食は豚の生姜焼きのようだ。俺の家は合鴨のパイ包み焼きだったが、豚の生姜焼きの方が好きだ。鴨は飽きた。
「王治ー! 玄ちゃんに中入ってもらいなさい! もう一人分ならあるから!」
「え! それ俺が食う分じゃねぇの!」
「うるさい健治! あんたは食いすぎ!」
中からおばさんと、王治の弟の声が聞こえる。
行武家の父親はずいぶんと前に蒸発したらしい。王治と弟の健治はおばさんが女手一つで育てている。彼女は、俺が尊敬する数少ない女性の一人だ。
「入る?」
王治が身体を斜めにして聞いてきたが、
「いや、いい。もう飯は食ったし」
と俺は断った。この団地の外に車も待たせているしな。
「あそ。で、一人でぼっこぼこにしてきたってどういうこと? 怪我してる様子もないけど」
鍵やら印鑑やら蝋燭やら靴べらやらごちゃごちゃといろいろ置かれている玄関に備え付けの靴箱に寄りかかり、王治が言う。
「あ、お前まさか、タイマンの約束があったからあの時自転車でさっさと帰ったわけ? なんで俺も誘わないんだよー」
俺と王治は、中学では不良の間で結構有名だったのだが、実際のところ嬉々として喧嘩に参加していたのは王治の方だった。俺はほぼ付き添い。その証拠に、俺にはあだ名はないが、王治には魔王なんていうあだ名がついた。考えた奴なかなかいいセンスしてるよな。
王治とは小五からの付き合いだが、こいつはその頃からわけのわからない性格だった。
高校に入ったら喧嘩はやめようとか言い出したのもこいつだ。クラスメートに対する口調を変え、一人称さえ『俺』から『僕』に変えたこいつの徹底ぶりは見ていて気持ち悪いくらいだ。
まぁそんなわけのわからん奴だからこそ、こんなに長い事つるんでいられるんだろうと思うけど。
七年だ。
その年月は、親友と呼べる程度には長い。
「いや、そうじゃなくて、八木原円に今後ちょっかいかけんなって言ってきた」
だからこう告げた時、王治の反応はある程度予想できた。
「……はぁ?」
王治は眉を上げて靴箱に寄りかかるのをやめた。
「おいおい、そりゃどういうことだよ。円ちゃん? え? お前、わざわざ円ちゃんのために北高行って、トップの奴ボコってきたわけ?」
「そうだ」
「え? なんで?」
「北高の奴らなら逆恨みで円襲うくらいのことしそうだろ」
「は? なんの逆恨み?」
「今日のことの」
王治は箸を靴箱の上に置いて額に手を当て、「うーん」と唸った。しかしすぐに残念そうな様子で首を振る。
「駄目だ。全然わかんねぇ。てゆうかお前、今日円ちゃんがあの後どうなったか知ってんの?」
なるほど。こいつは不良に拉致られた円がどうなったか確認することもしなかったわけだ。行武王治が優しげな見た目を裏切る冷血な男だということを俺はよく知っていた。
「お前、あの三人のこと知らないのか?」
そして世間知らず。こいつより俺の方がずっと常識を持っているはずだ。
「死神カルテットだよ。いや、死のカルテットだったか? まぁどっちでもいいか。俺らが小学生ん時北高で有名だったじゃねぇか」
「んー。聞いたことあるようなないような……?」
「とにかく、あの三人が行ったなら円を拉致した奴らは紙切れみたいに一蹴されて円は助けられたはずだ」
最初に会った時からどっかで見た顔だと思っていたのだ。八木原円と駅前の定食屋にいた二人の男。
そして家に帰ってから思い出した。
北高で有名だった不良四人組だ。
確かうちの一人はここ数年で死んだとかなんとかいう話を聞いたが……、ああ、だから今日も三人だったのか。しかし円は、あいつらとどういう関係なんだ。本当に予想を裏切る面白い女。
「ええとつまり、北高の奴らが、今日その死神なんとかってやつにボコられた腹いせに円ちゃんにちょっかいかける可能性があるから、先手を打ったってこと?」
王治は人差し指で円を描きながら考えて言った。
「まぁ、そうだな」
「お前が? なんで?」
俺はため息をついた。
今日の王治はいつにも増して理解が遅い。
「マド部の活動を忘れたのか? 『八木原円の不幸の回避とその対処法の研究』」
つまり、俺は円の不幸を前もって回避してやったに過ぎない。
「ああつまり、お前がやってやったことを円ちゃんに教えて恩に着せて嫌がらせするってこと?」
「は? 別に円に言う必要はない。それよりお前には明日、あいつを迎えに行ってやってほしいんだ。そういえば、明日の当番決めてなかっただろ」
「……」
王治は今まで見たことのなかった顔をした。
ものすごいまずい餌を食べさせられた時のうちのドーベルマンみたいな顔だ。
「……お前、自分の言ってることわかってんの?」
「お前こそ、日本語が理解できてるか? 明日はお前が円を迎えに行け」
俺は念のためもう一度言った。
「いや、それはわかってるけどさ……。どうしてお前が行かないんだよ」
「は? その話は最初にしただろ。円が朝大体何時に家を出ると思ってんだ。七時だぞ、七時。その時間俺はまだ寝てる」
俺は低血圧なのだ。
朝は弱い。
円に初めて会った日だって、始業式だからと無理矢理親父に起こされていなければ余裕で遅刻していただろう。そうなれば円にも会っていなかった。うん。縁というのは本当に面白い。
「いやだけど……。うん。まあいいや。俺が明日円ちゃんを迎えに行けばいいんだな? お前はそれを言うためだけに、夜の八時を回ったこの時間に俺んちに来たんだな?」
王治が細かく確認してくる。
「そうだ」
俺は頷いた。
「じゃあ頼んだぞ」
ようやく用件をすませることができたので、「じゃあな」と言って団地の狭い階段を降りる。俺が踊り場を曲がって下の階に降りたところで、ようやく王治ががちゃんと扉を閉めた音がした。
なんかあいつ、最後はすげぇ面白いものを見つけた時みたいな顔してたけど、ちゃんと俺が言ったこと理解してるんだろうな。俺の中を一瞬不安がよぎるが、まぁ長年の付き合いによる信頼というものを信用することにした。
郵便受けが八個並んでいる一階に降りると、小さな花壇の前を通り過ぎて団地の外に出る。
鈴木が運転席に座る車は外灯の灯りが届かないところに停めてあった。
「出していいぞ」
後部座席に乗ると、鈴木に命じる。
「かしこまりました」
鈴木は余計なことは何も聞かないし言わない。優秀な運転手だ。
俺は、今日家に帰ってから鈴木に渡された紙切れのことを思い出した。
八木原円から言付かったのだという。
『私は歩いて帰るけど、鈴木さんに責任はないから。
減俸とかそういうことしたらただじゃおかない。
具体的には、裸で外をうろつく変態趣味があるとか鼻の穴ほじりながらじゃないと用をたせないとかあることないこと学校でいいふらしてやる。 八木原円』
ああ本当に、面白い女。
俺は窓の外の、外灯の少ない住宅街を見ながら笑った
近年稀に見るヒットだ。
こいつはしばらく退屈しないに違いない。
「ずいぶんと、ご機嫌がよろしゅうございますね」
鈴木が言う。
「そうだな。いい夜だ」
俺はそう答えたのだった。